こんにちは、宅建受験生の皆さん!さかまさです。今日は、私が宅建試験に合格した時の体験を踏まえて、本当に効果的だった学習法をお伝えします。特に「過去問の活用法」と「問題集の選び方」について、詳しくお話しします。
宅建の勉強、最初は本当に大変でしたよね。私も挫折しそうになりました。でも、ある方法に出会ってから、グッと楽になったんです。それが「過去問マスター法」です!
過去問マスター法:4つの黄金ステップ
この方法、本当におすすめです。私自身、これで苦手だった権利関係も克服できました!
① 正誤の根拠を徹底解明
単に正解を覚えるのではなく、なぜその答えが正しいのか(または間違っているのか)を深く理解します。これにより、似た問題にも対応できる力が身につきます。
② 知識の枝葉を広げる
一つの問題から関連する知識を広げていきます。例えば、借地借家法の問題なら、正当事由や建物賃貸借の特徴など、関連する知識を整理します。これにより、体系的な理解が深まります。
③ 間違いを正しく直す力を磨く
誤った選択肢を正しい内容に修正する練習をします。これにより、法律の細かいニュアンスまで理解できるようになります。
④ 出題者の目線で考える
自分で引っ掛け問題を作ってみます。これにより、本番での思わぬ落とし穴を避けられるようになります。
例えば、遺産分割の問題。最初は難しく感じましたが、この方法で深掘りしていくうちに、すっきり理解できるようになりました。
具体例:2019年の問題6
問題:遺産分割に関する次の記述のうち、民法の規定および判例によれば正しいものはどれか
コードをコピーする被相続人は遺言によって遺産分割を禁止することはできず、共同相続人は遺産分割協議によって遺産の全部または一部の分割をすることができる。
これ、間違いなんです。実は、被相続人は遺言で5年以内なら遺産分割を禁止できるんですよ。
ここから関連知識を広げると:
- 遺産分割禁止の方法は4つある(遺言、協議、調停、審判)
- 禁止期間は5年以内だけど、更新できる
- 第三者に対抗するには登記が必要
さらに、正しい選択肢を作ってみると:
「被相続人は遺言によって5年を超えない期間において遺産分割を禁止することができる。」
引っ掛け問題を作るなら:
「共同相続人は協議によって5年を超えない期間において遺産の全部または一部の遺産分割を禁止することができるが、その期間を更新することはできない。」
こうやって広げていくと、徐々に全体像が見えてきて、理解が深まるんです。
最強問題集の選び方
問題集選びって悩みますよね。私も最初は迷いました。でも、以下のポイントを意識したら、ぴったりの一冊に出会えました!
① レイアウトは「左が問題、右が解説」がおすすめ
これなら、問題を解いてすぐに解説を確認できるので、効率的に学習できます。
② 自分にとって見やすいものを選ぶ
文字の大きさ、色使い、図表の配置など、自分の目に優しいものを選びましょう。長時間勉強するので、この点は重要です。
③ 初心者の方は、最初は解説から読むのがいいですよ
解説を読んでから問題に取り組むことで、理解を深めた状態で問題に挑戦できます。
私のおすすめは「宅建塾」や「宅建学院パーフェクト宅建4分野別過去問題集」です。これらは解説が丁寧で、初心者の方にも優しい内容になっています。
効果的な学習法のポイント
- 最初は解説から読む:これ、本当に効果的です!理解を深めてから問題に取り組めるので、挫折しにくくなります。
- 問題集を読んでからテキストを選ぶ:問題集で全体像を掴んでからテキストを読むと、重要ポイントが分かりやすくなります。
- テキストから読み始めない:最初からテキストを読むと、どこが重要か分からず挫折しやすいので注意!
- マーカーを引く必要はない:時間の無駄になりがちです。代わりに、重要ポイントをノートにまとめる方が効果的です。
みなさん、これらの方法を試してみてください。きっと学習効率がグッと上がるはずです。私自身、この方法で勉強時間を半分以下に減らせました!
宅建試験、確かに大変です。でも、コツさえつかめば、必ず合格できます。一緒に頑張りましょう!皆さんなら絶対にできます。
次回予告
次回は、私が実際に使って良かったテキストについて詳しくお話しします。各テキストの特徴や、どんな人におすすめかなど、具体的にお伝えする予定です。お楽しみに!
疑問や不安があれば、いつでも相談してくださいね。「この分野が苦手」「時間が足りない」など、具体的な悩みにも対応します。皆さんの合格を心から応援しています。一緒に頑張りましょう!


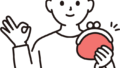

コメント