- 著名講師の分析に基づく出題傾向
- 権利関係(問1~問14)
- 宅建業法(問15~問34)
- 【問15】宅建業法(免許制度)★★★
- 【問16】宅建業法(欠格事由)★★
- 【問17】宅建業法(標識)★★★
- 【問18】宅建業法(従業者名簿)★★★
- 【問19】宅建業法(宅地建物取引士)★★
- 【問20】宅建業法(専任の宅地建物取引士)★★
- 【問21】宅建業法(営業保証金)★★
- 【問22】宅建業法(保証協会)★★
- 【問23】宅建業法(媒介契約)★★★
- 【問24】宅建業法(指定流通機構)★★★
- 【問25】宅建業法(重要事項説明)★★★
- 【問26】宅建業法(37条書面)★★★
- 【問27】宅建業法(報酬)★★★
- 【問28】宅建業法(監督処分)★★
- 【問29】宅建業法(罰則)★★
- 【問30】宅建業法(業者名簿)★★★
- 【問31】宅建業法(クーリングオフ)★★
- 【問32】宅建業法(損害賠償額の予定等)★★
- 【問33】宅建業法(瑕疵担保責任の特約の制限)★★
- 【問34】宅建業法(手付金等の保全措置)★★
- 法令上の制限(問35~問42)
- 税・その他(問43~問50)
- 権利関係(問1~問14)解説
- 宅建業法(問15~問34)解説
- 法令上の制限(問35~問42)解説
- 税・その他(問43~問50)解説
- 2025年宅建試験 最終学習ガイド
著名講師の分析に基づく出題傾向
主要講師陣の予想
- 吉野先生(日建学院・元大原講師):法改正問題の重要性を強調
- 田中嵩二先生(宅建業界の専門家):トレンド性の高い出題を予測
- 横田講師(20年以上の指導歴、1,000人以上の合格者輩出):基礎の正確性重視
- アガルート講師陣(高合格率で評価):改正民法と宅建業法の連携出題を予想
2025年重要改正ポイント
- 宅建業法の大幅改正(令和7年4月1日施行)
- 建築基準法4号特例の縮小
- 相続登記義務化の本格運用
- デジタル化推進関連
- 住宅ローン減税の継続措置
権利関係(問1~問14)
【問1】民法(意思表示)★★
AがBに対して土地の売却の意思表示をした場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
- Aが錯誤により意思表示をした場合、その意思表示は常に無効である。
- Aが詐欺により意思表示をした場合、その意思表示は無効である。
- Aが強迫により意思表示をした場合、その意思表示を取り消すことができる。
- Aが心裡留保により意思表示をした場合、その意思表示は常に無効である。
【問2】民法(代理)★★★
Aが代理人Bに土地の売却を委任した場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- Bが代理権を有することを相手方が知らなかった場合でも、表見代理が成立することがある。
- Bが代理権の範囲を超えて契約をした場合、Aがその契約を追認すれば有効となる。
- Bが自己契約をした場合、原則として無権代理となる。
- Aが死亡した場合、委任契約は当然に終了し、Bの代理権も消滅する。
【問3】民法(物権変動)★★★
不動産の物権変動に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 売買契約が成立すれば、登記がなくても買主は所有権を取得する。
- 不動産の物権変動を第三者に対抗するためには、必ず登記が必要である。
- 相続による所有権の取得には、登記は対抗要件ではない。
- 時効取得による所有権の取得には、登記は不要である。
【問4】民法(抵当権)★★★
抵当権に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 抵当権者は、抵当不動産を直接占有することができる。
- 抵当権の被担保債権が消滅すれば、抵当権も消滅する。
- 抵当権は、債務者以外の第三者が所有する不動産には設定できない。
- 抵当権の実行は、債務の弁済期が到来していなくても可能である。
【問5】民法(相続)★★★
相続に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 相続人は、相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、相続の承認又は放棄をしなければならない。
- 相続放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなされる。
- 遺産分割協議は、相続人全員の合意がなければ成立しない。
- 法定相続分と異なる割合での遺産分割は認められない。
【問6】借地借家法(借地権)★★
借地権に関する次の記述のうち、借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 普通借地権の存続期間は、最低30年である。
- 定期借地権の契約は、必ず公正証書により締結しなければならない。
- 借地権者は、地主の承諾なく建物の増改築を行うことができる。
- 借地権の譲渡には、地主の承諾が必要である。
【問7】借地借家法(借家権)★★
借家権に関する次の記述のうち、借地借家法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 定期建物賃貸借契約は、公正証書により締結しなければならない。
- 普通建物賃貸借契約において、1年未満の期間を定めた場合は期間の定めのないものとみなされる。
- 賃貸人が正当事由なく更新を拒絶することはできない。
- 定期建物賃貸借契約では、契約の更新がない。
【問8】区分所有法★★
区分所有建物に関する次の記述のうち、建物の区分所有等に関する法律の規定によれば、正しいものはどれか。
- 管理者は、区分所有者でなければならない。
- 規約の設定・変更・廃止は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要である。
- 専有部分の修繕は、管理組合の承認が必要である。
- 建物の建替えは、区分所有者及び議決権の各3分の2以上の多数による集会の決議が必要である。
【問9】不動産登記法(相続登記義務化)★★★
相続登記の義務化に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならない。
- 相続登記義務化の対象は、令和6年4月1日以降に発生した相続のみである。
- 正当な理由がない場合の過料は50万円以下である。
- 遺産分割協議が整わない場合でも、3年以内に遺産分割に基づく登記をしなければならない。
【問10】民法(債権譲渡)★★
債権譲渡に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 債権譲渡は、債務者の承諾なく行うことができる。
- 債権譲渡を債務者に対抗するためには、譲渡人が債務者に通知するか、債務者が承諾する必要がある。
- 譲渡禁止特約がある債権は、絶対に譲渡することができない。
- 債権譲渡の通知は、確定日付のある証書によることが望ましい。
【問11】民法(不法行為)★★
不法行為に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 不法行為による損害賠償請求権の消滅時効は、損害及び加害者を知った時から5年である。
- 精神的損害に対する慰謝料は、財産権の侵害があった場合のみ認められる。
- 過失がなければ、不法行為責任は生じない。
- 被害者に過失があった場合でも、損害賠償額の減額はされない。
【問12】民法(時効)★★
時効に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 取得時効の期間は、善意無過失の場合は10年、その他の場合は20年である。
- 消滅時効は、当事者が援用しなくても、裁判所が職権で適用する。
- 時効の利益は、予め放棄することができる。
- 時効の完成後であれば、いつでも時効の利益を放棄することができる。
【問13】民法(売買契約)★★
売買契約に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 売主は、買主に対して売買の目的物を引き渡す義務を負う。
- 買主は、売主に対して代金を支払う義務を負う。
- 売買契約において、所有権の移転時期の特約は無効である。
- 契約不適合責任は、買主が契約不適合を知った時から1年以内に通知しなければならない。
【問14】民法(賃貸借契約)★★
賃貸借契約に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 賃貸借契約の存続期間は、最長50年である。
- 賃借人は、賃貸人の承諾なく賃借権を譲渡することができる。
- 賃貸人は、賃借人に対して使用収益させる義務を負う。
- 賃料の支払時期は、必ず月末と定めなければならない。
宅建業法(問15~問34)
【問15】宅建業法(免許制度)★★★
宅地建物取引業の免許に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 国土交通大臣免許の申請は、必ず主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事を経由しなければならない。
- 宅地建物取引業の免許の有効期間は5年である。
- 法人が免許を受ける場合、その役員のうち1人は宅地建物取引士でなければならない。
- 免許の更新申請は、免許の有効期間満了の日の30日前までにしなければならない。
【問16】宅建業法(欠格事由)★★
宅地建物取引業の免許の欠格事由に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者は、免許を受けることができない。
- 宅地建物取引業法違反により罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わった日から5年を経過しない者は、免許を受けることができない。
- 心身の故障により宅地建物取引業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定める者は、免許を受けることができない。
- 暴力団員である者は、免許を受けることができない。
【問17】宅建業法(標識)★★★
宅地建物取引業者が事務所に掲示する標識に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 専任の宅地建物取引士の氏名を記載しなければならない。
- 専任の宅地建物取引士の人数を記載しなければならない。
- 宅地建物取引業に従事する者の人数は記載する必要がない。
- 事務所の代表者氏名は記載する必要がない。
【問18】宅建業法(従業者名簿)★★★
宅地建物取引業者が事務所ごとに備える従業者名簿に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 従業者の氏名を記載しなければならない。
- 従業者の生年月日を記載しなければならない。
- 従業者の主たる職務内容を記載しなければならない。
- 宅地建物取引士であるか否かの別を記載しなければならない。
【問19】宅建業法(宅地建物取引士)★★
宅地建物取引士に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 宅地建物取引士資格試験は、年2回実施される。
- 宅地建物取引士の登録は、試験に合格すれば自動的に行われる。
- 宅地建物取引士証の有効期間は5年である。
- 宅地建物取引士は、他の宅地建物取引業者の専任の宅地建物取引士になることができない。
【問20】宅建業法(専任の宅地建物取引士)★★
専任の宅地建物取引士に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 事務所ごとに、業務に従事する者5人に1人以上の割合で専任の宅地建物取引士を置かなければならない。
- 専任の宅地建物取引士は、その事務所に常勤しなければならない。
- 専任の宅地建物取引士は、他の宅地建物取引業者の専任の宅地建物取引士になることができる。
- 宅地建物取引業者が法人である場合、その役員は専任の宅地建物取引士になることができる。
【問21】宅建業法(営業保証金)★★
営業保証金に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 主たる事務所には1,000万円、その他の事務所には各500万円の営業保証金を供託しなければならない。
- 営業保証金は、現金以外では供託することができない。
- 営業保証金の供託をしなければ、営業を開始することができない。
- 営業保証金の還付を受けるためには、免許権者の承認が必要である。
【問22】宅建業法(保証協会)★★
宅地建物取引業保証協会に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 保証協会の社員となることで、営業保証金の供託に代えることができる。
- 保証協会に納付する弁済業務保証金分担金は、主たる事務所60万円、その他の事務所各30万円である。
- 保証協会の社員は、一般保証協会と不動産保証協会の両方に加入することができる。
- 保証協会から脱退した場合は、営業保証金を供託しなければならない。
【問23】宅建業法(媒介契約)★★★
媒介契約に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 一般媒介契約の有効期間に制限はない。
- 専任媒介契約の有効期間は3ヶ月を超えることができない。
- 専属専任媒介契約では、依頼者は他の宅地建物取引業者に重ねて媒介を依頼することができる。
- 媒介契約書面は、契約締結後遅滞なく交付すればよい。
【問24】宅建業法(指定流通機構)★★★
指定流通機構(レインズ)への登録に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 一般媒介契約でも登録義務がある。
- 専任媒介契約の場合、契約締結の日から7日以内に登録しなければならない。
- 専属専任媒介契約の場合、契約締結の日から10日以内に登録しなければならない。
- 令和7年1月1日施行の改正により、登録項目の厳格化は行われていない。
【問25】宅建業法(重要事項説明)★★★
重要事項説明に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 重要事項説明は、宅地建物取引士でなければ行うことができない。
- 重要事項説明書面には、宅地建物取引士が記名押印しなければならない。
- 重要事項説明は、契約締結前に行わなければならない。
- 重要事項説明は、必ず対面で行わなければならない。
【問26】宅建業法(37条書面)★★★
37条書面に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 37条書面の交付は、宅地建物取引士でなければ行うことができない。
- 37条書面には、宅地建物取引士の記名押印が必要である。
- 37条書面は、契約締結前に交付しなければならない。
- 37条書面の交付義務は、売買契約にのみ適用される。
【問27】宅建業法(報酬)★★★
宅地建物取引業者が受け取ることができる報酬に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 宅地の売買の媒介の場合、売主・買主それぞれから代金の3%の報酬を受け取ることができる。
- 建物の売買の媒介の場合、売主・買主それぞれから代金の3%+6万円の報酬を受け取ることができる。
- 低廉な空き家等の売買の媒介の場合、特例により通常の報酬額を上回る報酬を受け取ることができる。
- 報酬は、契約成立前であっても受け取ることができる。
【問28】宅建業法(監督処分)★★
宅地建物取引業者に対する監督処分に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 指示処分は、宅地建物取引業法違反があった場合に行われる。
- 業務停止処分の期間は、1年を超えることができない。
- 免許取消処分を受けた者は、処分の日から5年間は免許を受けることができない。
- 監督処分は、聴聞を行った後でなければ行うことができない。
【問29】宅建業法(罰則)★★
宅地建物取引業法の罰則に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 無免許営業をした者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられる。
- 重要事項説明を行わなかった者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる。
- 37条書面を交付しなかった者は、6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる。
- 帳簿を備えなかった者は、10万円以下の過料に処せられる。
【問30】宅建業法(業者名簿)★★★
宅地建物取引業者名簿に関する次の記述のうち、令和7年4月1日施行の法改正後において、正しいものはどれか。
- 専任の宅地建物取引士の氏名を記載しなければならない。
- 専任の宅地建物取引士の氏名の記載は不要となった。
- 業者名簿の記載事項に変更はない。
- 事務所の代表者に関する情報は記載不要である。
【問31】宅建業法(クーリングオフ)★★
クーリングオフに関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- クーリングオフができるのは、宅地建物取引業者が自ら売主となる場合である。
- クーリングオフの期間は、クーリングオフについて告げられた日から8日間である。
- 宅地建物取引業者の事務所で契約をした場合、クーリングオフはできない。
- クーリングオフの効力は、書面を発した時に生ずる。
【問32】宅建業法(損害賠償額の予定等)★★
損害賠償額の予定等に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 宅地建物取引業者が自ら売主となる場合、損害賠償額の予定をすることはできない。
- 損害賠償額の予定又は違約金の額は、代金の10分の2を超えることができない。
- 損害賠償額の予定と違約金を併せて定める場合、その合計額が代金の10分の2を超えてはならない。
- この規定は、宅地建物取引業者間の取引にも適用される。
【問33】宅建業法(瑕疵担保責任の特約の制限)★★
契約不適合責任に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 宅地建物取引業者が自ら売主となる場合、買主が契約不適合を知った時から1年以内に通知しなければ契約不適合責任を追及できない旨の特約は有効である。
- 宅地建物取引業者が自ら売主となる場合、引渡しの日から2年間責任を負う旨の特約は有効である。
- 民法の規定よりも買主に不利な特約は無効である。
- この規定は、宅地建物取引業者間の取引には適用されない。
【問34】宅建業法(手付金等の保全措置)★★
手付金等の保全措置に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 宅地建物取引業者が自ら売主となって新築住宅を販売する場合、代金の額が1,000万円を超え、かつ手付金等の額が代金の10分の1を超えるときは保全措置を講じなければならない。
- 既存住宅の場合は、代金の額や手付金等の額に関係なく、保全措置を講じる必要はない。
- 保全措置として、銀行等による保証又は保険事業者による保証保険が利用できる。
- 保全措置を講じた場合、その旨を重要事項説明書面に記載する必要はない。
法令上の制限(問35~問42)
【問35】都市計画法(開発許可)★★★
開発許可に関する次の記述のうち、都市計画法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 市街化区域内において行う開発行為で、その規模が1,000平方メートル未満であるものは、開発許可を受ける必要がない。
- 市街化調整区域内では、原則として開発行為は禁止されている。
- 準都市計画区域内において、農業を営む者の居住用建築物の建築を目的とした1,000平方メートルの土地の区画形質の変更には、都道府県知事の許可が必要である。
- 都市計画区域外では、開発許可は不要である。
【問36】建築基準法(4号特例)★★★
建築基準法における「4号特例」の改正に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 2025年4月1日以降も従来の4号特例は継続される。
- 4号建築物は新2号建築物と新3号建築物に再分類される。
- 省エネ基準適合義務化とは関係のない改正である。
- 建築確認審査の省略範囲が拡大される。
【問37】建築基準法(建蔽率)★★
建蔽率に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 建蔽率は、建築物の建築面積の敷地面積に対する割合である。
- 防火地域内にある耐火建築物は、建蔽率の制限が10分の1緩和される。
- 街角にある敷地では、建蔽率の制限が10分の1緩和される。
- 準防火地域内にある準耐火建築物は、建蔽率の制限が10分の1緩和される。
【問38】建築基準法(容積率)★★
容積率に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 容積率は、建築物の床面積の合計の敷地面積に対する割合である。
- 前面道路の幅員が12メートル未満の場合、前面道路の幅員による容積率の制限は適用されない。
- 共同住宅の共用廊下の面積は、容積率の算定に含まれる。
- 地下室の住宅部分の床面積は、住宅の床面積の合計の3分の1を限度として容積率の算定に含まれない。
【問39】国土利用計画法★★
国土利用計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 市街化区域内の2,000平方メートルの土地売買契約には事前届出が必要である。
- 市街化調整区域内の5,000平方メートルの土地売買契約には事前届出が必要である。
- 都市計画区域外の10,000平方メートルの土地売買契約には事前届出が必要である。
- 注視区域内では、面積に関係なく事前届出が必要である。
【問40】農地法★★
農地法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 農地を農地以外のものにする場合は、都道府県知事の許可が必要である。
- 農地の所有権を移転する場合は、農業委員会の許可が必要である。
- 市街化区域内の農地を転用する場合は、農業委員会への届出で足りる。
- 農地法の許可を受けずに行った農地の権利移動は無効である。
【問41】土地区画整理法★★
土地区画整理法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 土地区画整理事業の施行地区内では、土地区画整理法76条の許可を受けなければ建築物を建築することができない。
- 仮換地の指定があった場合、従前の土地に係る所有権は消滅する。
- 換地処分の公告があった日の翌日から、仮換地は正式な換地となる。
- 保留地は、土地区画整理組合のみが取得することができる。
【問42】その他の法令★★
宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 宅地造成工事規制区域内で宅地造成に関する工事を行う場合は、都道府県知事の許可が必要である。
- 宅地造成工事規制区域は、国土交通大臣が指定する。
- 高さ1メートルの擁壁を設置する場合は、許可が必要である。
- 宅地造成工事規制区域内では、すべての建築行為が禁止される。
税・その他(問43~問50)
【問43】不動産取得税★★
不動産取得税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 不動産取得税は国税である。
- 相続による不動産の取得には不動産取得税が課税される。
- 住宅用土地の取得については、課税標準の特例措置がある。
- 不動産取得税の税率は、すべての不動産について4%である。
【問44】固定資産税★★
固定資産税に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 固定資産税は市町村税である。
- 住宅用地については、課税標準の特例措置がある。
- 新築住宅については、固定資産税の減額措置がある。
- 固定資産税の納期は、年1回である。
【問45】所得税(譲渡所得)★★★
居住用財産の譲渡所得の特例に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 3,000万円の特別控除の適用を受けるためには、譲渡した年の1月1日における所有期間が10年を超えている必要がある。
- 軽減税率の特例の適用を受けるためには、譲渡した年の1月1日における所有期間が10年を超えている必要がある。
- 買換えの特例と3,000万円の特別控除は併用することができる。
- 特例の適用を受けるためには、譲渡の年の前年及び前々年に他の居住用財産の特例の適用を受けていてはならない。
【問46】住宅ローン減税★★★
2025年度税制改正における住宅ローン減税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 住宅ローン減税制度は2024年度で終了する。
- 子育て世帯等に対する借入限度額の上乗せ措置が継続される。
- 既存住宅のリフォームに対する特例措置は廃止される。
- 2025年度から控除率が引き下げられる。
【問47】地価公示法★★
地価公示法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 地価公示は、国土交通大臣が毎年1月1日時点の正常な価格を公示する。
- 標準地の正常な価格は、不動産鑑定士の鑑定評価を求めて決定される。
- 地価公示の対象となるのは、都市計画区域内の土地のみである。
- 公示価格は、売買や課税の基準として必ず使用しなければならない。
【問48】統計★★★
令和6年度の土地・住宅に関する統計について、正しいものはどれか。
- 新設住宅着工戸数は、前年度と比較して増加している。
- 地価公示による全国平均変動率は、住宅地・商業地ともに上昇している。
- 住宅・土地統計調査による空き家率は、前回調査と比較して減少している。
- 法人企業統計調査による不動産業の経常利益は、前年同期と比較して減少している。
【問49】5点免除科目(住宅金融支援機構)★★
独立行政法人住宅金融支援機構に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 住宅金融支援機構は、一般の金融機関と直接競合する業務は行わない。
- フラット35は、住宅金融支援機構が直接融資する制度である。
- 住宅金融支援機構の業務の対象となる住宅は、自ら居住するための住宅に限られる。
- 住宅金融支援機構は、災害復興住宅融資を行うことができない。
【問50】5点免除科目(不当景品類及び不当表示防止法)★★
不当景品類及び不当表示防止法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 不当景品類及び不当表示防止法は、公正な競争を確保することを目的としている。
- 不動産の表示に関する公正競争規約は、不動産公正取引協議会が設定している。
- 徒歩による所要時間は、道路距離80メートルにつき1分間を要するものとして算出して表示する。
- 電車の所要時間は、日中平常時の最短時間を乗車時間として表示することができる。
解答一覧
権利関係(問1~問14) 1-3, 2-1, 3-1, 4-2, 5-4, 6-1, 7-1, 8-2, 9-1, 10-3, 11-1, 12-1, 13-3, 14-3
宅建業法(問15~問34) 15-2, 16-※, 17-2, 18-2, 19-3, 20-3, 21-3, 22-3, 23-2, 24-2, 25-4, 26-2, 27-3, 28-4, 29-1, 30-2, 31-※, 32-3, 33-1, 34-3
法令上の制限(問35~問42) 35-3, 36-2, 37-4, 38-4, 39-2, 40-※, 41-1, 42-1
税・その他(問43~問50) 43-3, 44-4, 45-2, 46-2, 47-2, 48-2, 49-1, 50-※
※印は全選択肢が正しい問題
詳細解説
権利関係(問1~問14)解説
【問1】民法(意思表示)解説
正解肢3について: 民法96条1項により、強迫による意思表示は取り消すことができます。強迫は相手方又は第三者からの害悪の告知により、表意者が恐怖心を抱いて行った意思表示であり、取消権の行使により無効となります。
誤り肢の解説:
- 錯誤について: 民法95条により、錯誤による意思表示は「取り消すことができる」のであって、常に無効ではありません。表意者に重大な過失があった場合や、法律行為の基礎とした事情について表意者が責任を負うべき場合は取り消せません。
- 詐欺について: 民法96条1項により、詐欺による意思表示は「取り消すことができる」のであって、無効ではありません。取消しまでは有効な法律行為として扱われます。
- 心裡留保について: 民法93条により、心裡留保による意思表示は原則として有効です。ただし、相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができた場合は無効となります。
ポイント: 意思表示の効力は「無効」と「取消し」で大きく異なります。無効は当初から効力がなく、取消しは取消権行使により遡及的に無効となります。
【問9】不動産登記法(相続登記義務化)解説
【2024年4月1日施行・2025年本格運用】 相続登記義務化は令和6年4月1日に施行され、2025年で2年目を迎える重要制度です。
正解肢1について: 不動産登記法第76条の2により、相続により所有権を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。これが相続登記義務化の根幹となる規定です。
義務の内容:
- 期限: 所有権取得を知った日から3年以内
- 過料: 正当な理由なく申請を怠った場合は10万円以下(50万円ではない)
- 対象: 令和6年4月1日より前に発生した相続についても、同日から3年以内(令和9年3月31日まで)に登記申請が必要
相続人申告登記制度: 遺産分割協議が3年以内に整わない場合は、まず「相続人申告登記」により義務を履行し、遺産分割成立後3年以内に正式な相続登記を行います。
出題予想: 権利関係分野で2025年試験の超重要ポイントです。期限、過料額、施行日前相続の取扱いを正確に覚えてください。
宅建業法(問15~問34)解説
【問17】宅建業法(標識)解説
【2025年重要法改正】 令和7年4月1日施行の宅地建物取引業法施行規則改正により、標識の記載事項が大幅に変更されました。
正解肢2について: 新しい施行規則第19条により、標識には「専任の宅地建物取引士の人数」を記載することが義務付けられました。個人名ではなく人数のみの記載となります。
改正内容の詳細:
- 削除された項目: 「専任の宅地建物取引士の氏名」(個人情報保護の観点から)
- 新たに追加された項目: 専任の宅地建物取引士の人数、宅地建物取引業に従事する者の数、この事務所の代表者氏名(政令使用人)
改正の背景: 個人情報保護法の強化に伴い、従業者のプライバシー保護を図りつつ、事務所の体制に関する適切な情報提供を行うための改正です。
出題予想: この改正は2025年試験で確実に出題される最重要ポイントです。新旧の違いを正確に把握してください。
【問18】宅建業法(従業者名簿)解説
【2025年重要法改正】 令和7年4月1日施行の宅地建物取引業法施行規則改正により、従業者名簿の記載事項が変更されました。
誤り肢2について: 改正された施行規則第17条の2により、従業者名簿から「生年月日」の記載が削除されました。これまで必要だった生年月日、性別、住所の3項目がすべて削除され、従業者のプライバシー保護が図られました。
削除された記載事項: 従業者の住所、従業者の生年月日、従業者の性別 継続する記載事項: 氏名、主たる職務内容、宅地建物取引士であるか否かの別、当該事務所の従業者となった年月日、当該事務所の従業者でなくなったときは、その年月日
改正の背景: 従業者名簿は取引の関係者が閲覧可能であるため、個人情報保護法の観点から、必要以上の個人情報の記載を避ける必要性が高まったことが改正の理由です。
出題予想: 標識と並んで2025年試験で確実に出題される最重要改正ポイントです。何が削除されたかを正確に記憶してください。
法令上の制限(問35~問42)解説
【問36】建築基準法(4号特例)解説
【2025年重要法改正】 2025年4月1日以降に着工する建築物から、建築基準法における「4号特例」が大幅に見直されました。
正解肢2について: 従来の「4号建築物」の区分が廃止され、新たに「新2号建築物」と「新3号建築物」に再分類されます。これにより、審査の対象や内容が細分化され、より適切な審査が可能となります。
改正の背景:
- 2050年カーボンニュートラル実現: 省エネ基準適合義務化への対応
- 自然災害対策: 地震や台風に対する住宅の安全性確保
- 住宅重量増加への対応: 断熱材や設備搭載による重量増加に見合う強度確保
改正前の4号建築物: 木造で階数が2以下、延べ面積500㎡以下、高さ13m以下、軒高9m以下で構造計算や省エネ基準適合性審査が省略されていました。
改正後の新分類: 新2号建築物(より小規模な建築物で審査省略範囲縮小)と新3号建築物(中規模な建築物でより厳格な審査)に再分類されます。
実務への影響: 建築確認申請の審査期間延長の可能性、設計・施工コストの増加、より詳細な構造計算書の提出が必要、省エネ性能の証明書類追加などが予想されます。
出題予想: 法令上の制限分野で2025年試験の最重要出題ポイントです。改正の背景と新分類を正確に理解してください。
税・その他(問43~問50)解説
【問46】住宅ローン減税解説
【2025年度税制改正】 住宅取得支援のための重要な措置が2025年度も継続されることとなりました。
正解肢2について: 2025年度税制改正では、住宅ローン減税の子育て世帯等に対する借入限度額の上乗せ措置が継続されます。これは少子化対策と住宅政策を連携させた重要な措置です。
2025年度住宅ローン減税の継続内容:
- 子育て世帯等への上乗せ措置: 19歳未満の子を有する世帯、夫婦合計所得が2,000万円以下の世帯が対象で、一般住宅で1,000万円、認定住宅等でさらに上乗せされます。
- 基本的な制度内容: 控除率0.7%(変更なし)、控除期間は新築住宅13年・既存住宅10年、所得制限は合計所得金額2,000万円以下
- 既存住宅リフォーム特例: 子育て対応リフォーム、バリアフリー改修、省エネ改修の特例措置が継続
政策的背景: 少子化対策(子育て世帯の住宅取得支援)、既存住宅活用(ストック活用型社会への転換)、環境配慮(省エネ住宅の普及促進)の3つの観点から継続措置が決定されました。
関連法令: 所得税法(住宅借入金等特別控除)、租税特別措置法、2025年3月31日国会成立の関連税制法により、これらの措置が法的に確定しています。
出題予想: 税・その他分野で2025年試験の重要ポイントです。継続措置の内容と対象世帯を正確に理解してください。
2025年宅建試験 最終学習ガイド
最重要法改正(確実に出題予想)★★★
- 標識・従業者名簿の記載事項変更(宅建業法):個人情報保護対応で2-3問確実出題
- 建築基準法4号特例の縮小(法令上の制限):カーボンニュートラル対応で新分類理解必須
- 相続登記義務化の本格運用(権利関係):2024年施行、2025年本格運用で詳細制度理解必要
- レインズ登録項目の厳格化(宅建業法):令和7年1月施行で登録期限と併せて出題
- 住宅ローン減税の継続措置(税・その他):子育て世帯上乗せ継続で少子化対策との関連理解
著名講師陣の共通見解
吉野先生(日建学院): 法改正問題は毎年2-3問出題、確実な得点源にすべき。「出るとこ!集中講座」での重点分野を毎日復習、本試験直前は全分野に触れる学習法が有効。
田中嵩二先生: 出題傾向・法改正のトレンド性を重視。2025年は特に宅建業法の改正問題が多い。基礎知識の正確性が合否を分ける。
横田講師(20年以上指導): 「何となく」の理解では通用しない傾向強まる。条文の正確な暗記が必要。1,000人以上の合格実績から見る重要ポイント重視。
アガルート講師陣: 改正民法と宅建業法の連携出題増加。フルカラーテキストでの視覚的記憶法推奨。高合格率講座での実績に基づく予想。
科目別攻略ポイント
権利関係(14問)目標得点:8-9問 基礎重視で意思表示、代理、物権変動の基本理解。相続登記義務化は確実に1問出題。1-2問の超難問は割り切って時間配分重視。
宅建業法(20問)目標得点:18-19問 法改正問題で標識・従業者名簿で確実に2問以上得点。基本制度の正確な理解。IT重説含む最新実務対応。近年細かい問題増加で満点狙いは危険。
法令上の制限(8問)目標得点:5-6問 開発許可の区域別面積要件の正確な暗記必須。4号特例改正は確実出題。建蔽率・容積率の基本。数字の暗記が得点を左右。
税・その他(8問)目標得点:6-7問 不動産取得税・固定資産税の特例措置詳細確認。譲渡所得の居住用財産特例要件・併用可否。住宅ローン減税2025年継続措置。統計問題で確実に1点。
合格ラインの予想
- 予想合格点: 35-37点(50点満点)
- 安全圏: 38点以上
- 各科目最低ライン: 権利関係8点、宅建業法16点、法令上の制限4点、税その他4点
試験当日の心構え
- 時間配分: 宅建業法30分、権利関係40分、法令上の制限25分、税その他25分
- 見直し順序: 宅建業法→税その他→法令上の制限→権利関係
- マークミス対策: 問題番号と解答番号の照合を5問ごとに実施
2025年10月19日の宅建試験、全力で頑張ってください!🏠📚✨

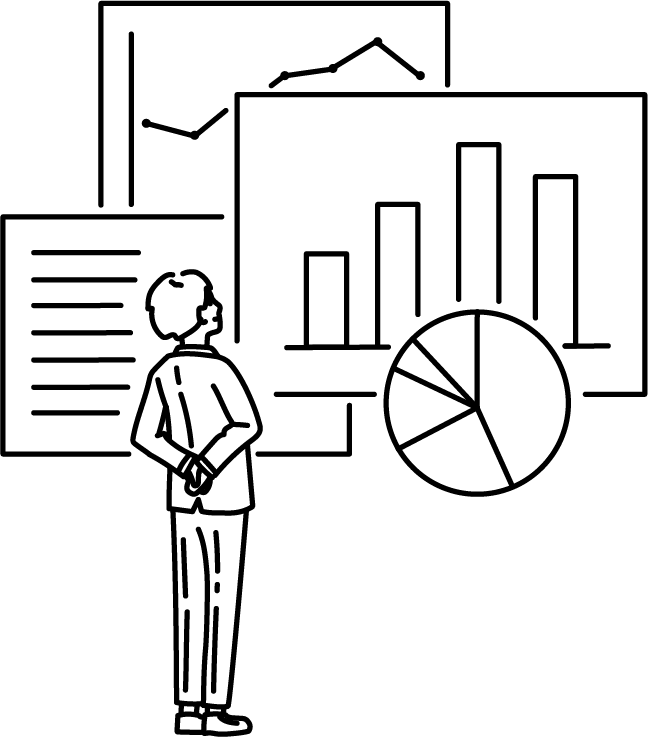


コメント