この記事は宅建試験まで残り少ない受験生のための完全網羅型対策記事です。重要数字、計算問題、頻出ポイントを表と図で分かりやすく解説します。
🔍 この記事で分かること
- ✅ 宅建試験の全分野(宅建業法・法令制限・民法等・税その他)の重要暗記事項
- ✅ 合格点を確実に取るための効率的勉強法
- ✅ 計算問題の解き方と重要数字の覚え方
- ✅ 試験当日の時間配分と解答戦略
- ✅ 過去問分析に基づく頻出問題対策
📖 目次
- 宅建試験概要と合格戦略
- 宅建業法完全攻略(20問)
- 法令上の制限対策(8問)
- 民法等重要ポイント(14問)
- 税・その他分野(8問)
- 計算問題完全マスター
- 試験当日の完全マニュアル
- よくある質問(FAQ)
🎯 宅建試験概要と合格戦略
📊 2025年宅建試験基本データ
| 項目 | 詳細 | 備考 |
|---|
| 試験日 | 2025年10月19日(第3日曜日) | 年1回実施 |
| 試験時間 | 13:00-15:00(120分) | 途中退出不可 |
| 問題数 | 50問(4択マークシート) | 各問2点 |
| 合格ライン | 32〜37点(例年) | 約70%の正答率 |
| 受験料 | 8,200円 | 一般財団法人不動産適正取引推進機構 |
| 合格率 | 約17%(過去5年平均) | 難易度の高い国家資格 |
🎯 分野別戦略マップ
| 分野 | 出題数 | 配点 | 目標得点 | 重要度 | 学習時間配分 | 主要対策 |
|---|
| 宅建業法 | 20問 | 40点 | 18問以上 | ★★★ | 40% | 暗記中心・確実に得点 |
| 法令制限 | 8問 | 16点 | 6問以上 | ★★☆ | 25% | 重要数字と計算問題 |
| 民法等 | 14問 | 28点 | 8問以上 | ★★☆ | 25% | 基本概念の理解 |
| 税・その他 | 8問 | 16点 | 5問以上 | ★☆☆ | 10% | 頻出分野に絞る |
| 合計 | 50問 | 100点 | 37点以上 | – | 100% | 効率重視 |
📈 過去5年合格点推移と受験データ
| 年度 | 合格点 | 合格率 | 受験者数 | 合格者数 | 傾向分析 |
|---|
| 2024年 | 38点 | 17.2% | 233,276人 | 40,025人 | 宅建業法重視継続 |
| 2023年 | 36点 | 17.2% | 233,276人 | 40,025人 | 法令制限で差 |
| 2022年 | 36点 | 17.0% | 226,048人 | 38,525人 | 民法改正影響 |
| 2021年 | 34点 | 17.9% | 209,749人 | 37,579人 | コロナ影響あり |
| 2020年 | 38点 | 17.6% | 204,163人 | 35,888人 | 例年並み |
💡 合格のポイント:宅建業法で18問以上取れれば合格確率が飛躍的に上がります
🏢 宅建業法完全攻略(20問)
🔢 絶対暗記!重要数字一覧表
免許・届出関係の重要数字
| 項目 | 期間・金額 | 語呂合わせ | 備考 |
|---|
| 宅建業免許有効期間 | 5年間 | 「ご」(5)年間有効 | 個人・法人共通 |
| 更新申請期間 | 満了90日前〜30日前 | 「苦(9)労さん(3)」 | この期間内必須 |
| 免許証交付期間 | 申請後30日以内 | 「みっ(3)か」月じゃなくて日 | 申請後 |
| 変更届出期間 | 変更後30日以内 | 変更は「みっ(3)か」以内 | 変更事実発生後 |
| 廃業届期間 | 廃業後30日以内 | 廃業も「みっ(3)か」以内 | 事実発生後 |
| 免許換え期間 | 30日以内 | 換えるのも「みっ(3)か」以内 | 事務所移転等 |
営業保証金・保証協会の金額表
| 事務所区分 | 営業保証金 | 保証協会分担金 | 比率 | 覚え方 |
|---|
| 本店 | 1,000万円 | 60万円 | 1:16.7 | 本店は「千(1000)万」「ろく(60)じゅう万」 |
| 支店1ヶ所 | 500万円 | 30万円 | 1:16.7 | 支店は「ごひゃく(500)万」「さんじゅう(30)万」 |
| 支店2ヶ所 | 1,500万円 | 90万円 | 1:16.7 | 本店+支店×2 |
| 支店3ヶ所 | 2,000万円 | 120万円 | 1:16.7 | 本店+支店×3 |
🎯 暗記のコツ:営業保証金と保証協会の比率は常に1:16.7(約1:17)
👥 宅建士設置基準と業務
宅建士設置義務一覧
【事務所での設置基準】
従業員数 1〜 5人 → 宅建士 1人以上
従業員数 6〜10人 → 宅建士 2人以上
従業員数11〜15人 → 宅建士 3人以上
従業員数16〜20人 → 宅建士 4人以上
※「5人に1人以上」の専任宅建士が必要
※分数で覚える:1/5以上
【案内所等での設置基準】
常に宅建士1人以上の設置が必要
(専任でなくてもOK)
宅建士の重要業務分類表
| 業務分類 | 業務内容 | 実施者 | 記名押印 | 罰則 |
|---|
| 独占業務 | 35条書面の説明 | 宅建士のみ | 必要 | 2年以下の懲役等 |
| 独占業務 | 35条書面への記名押印 | 宅建士のみ | 必要 | 同上 |
| 独占業務 | 37条書面への記名押印 | 宅建士のみ | 必要 | 同上 |
| 専任業務 | 契約締結等の業務 | 宅建士が専任 | – | 業務停止等 |
📋 35条書面 vs 37条書面 完全比較表
| 比較項目 | 35条書面(重要事項説明書) | 37条書面(契約書面) |
|---|
| 正式名称 | 重要事項説明書 | 契約書面 |
| 法的根拠 | 宅建業法35条 | 宅建業法37条 |
| 交付義務者 | 宅建士 | 宅建士 |
| 交付相手方 | 買主・借主(顧客のみ) | 当事者全員 |
| 交付時期 | 契約締結前 | 契約締結後遅滞なく |
| 説明義務 | あり(口頭説明必須) | なし(書面交付のみ) |
| 記名押印 | 宅建士が必要 | 宅建士が必要 |
| 目的 | 契約判断材料の提供 | 契約内容の確定 |
📝 35条書面記載事項分類表
🏠 物件関係記載事項
| 大分類 | 中分類 | 具体的記載事項 | 売買 | 賃貸借 |
|---|
| 基本情報 | 登記関係 | 登記名義人・登記年月日 | ○ | ○ |
| 物理的事項 | 物件特定 | 所在・地番・家屋番号・種別・構造・床面積 | ○ | ○ |
| 権利関係 | 権利制限 | 所有権以外の権利・登記された権利の制限 | ○ | ○ |
| 法的制限 | 公法制限 | 都市計画法・建築基準法等の制限 | ○ | ○ |
| 設備関係 | インフラ | 電気・ガス・上下水道の整備状況 | ○ | ○ |
| その他 | 特記事項 | 私道負担・土壌汚染等 | ○ | ○ |
💰 金銭・契約関係記載事項
| 分類 | 売買契約特有 | 賃貸借契約特有 | 共通事項 |
|---|
| 基本金額 | 代金・交換差金 | 借賃・権利金 | – |
| その他金銭 | 代金等以外の金銭 | – | – |
| 保証・精算 | 手付金等の保全措置 | 敷金等の精算 | – |
| 契約解除 | 契約解除に関する事項 | 契約解除に関する事項 | ○ |
| 損害賠償 | 損害賠償・違約金 | 損害賠償・違約金 | ○ |
| 金銭貸借 | 金銭の貸借あっせん | 金銭の貸借あっせん | ○ |
⚖️ 宅建業法規制フローチャート
【宅建業務の流れと規制ポイント】
🔍 物件調査・広告準備
↓
❌ 【規制】許可等の処分前は広告禁止
↓
📢 広告開始(許可等処分後)
↓
🏠 物件案内・営業活動
↓
📋 重要事項説明(35条書面)
・宅建士が説明・記名押印
・契約締結前に実施
↓
❌ 【規制】許可等の処分前は契約締結禁止
↓
🤝 契約締結(許可等処分後)
・手付金は代金の20%以下
↓
📄 契約書面交付(37条書面)
・宅建士が記名押印
・遅滞なく交付
↓
✅ 取引完了
💰 手付金・報酬額の重要制限
手付金制限表
| 項目 | 制限内容 | 根拠条文 | 違反の効果 |
|---|
| 手付金額 | 代金の20%以下 | 宅建業法39条 | 業務停止処分等 |
| 手付金の性質 | 解約手付と推定 | 同法39条 | 当事者間の合意優先 |
| 手付放棄・倍返し | 相手方の履行着手前まで | 同法39条 | 着手後は解除不可 |
報酬額算定表(売買・交換)
| 物件価格 | 報酬率上限 | 計算例 |
|---|
| 200万円以下 | 5.5%以内 | 200万円×5.5%=11万円 |
| 200万円超400万円以下 | 4.4%以内+2.2万円 | (300万円-200万円)×4.4%+11万円=15.4万円 |
| 400万円超 | 3.3%以内+13.2万円 | (500万円-400万円)×3.3%+26.4万円=29.7万円 |
💡 報酬計算の裏技:「5・4・3の法則」400万円超は価格×3%+6万円(+消費税)
📋 法令上の制限対策(8問)
🏙️ 用途地域13種類完全分類表
住居系用途地域(8種類)
| 用途地域名 | 略称 | 主な特徴 | 建築可能建物例 | 建築不可建物例 | 建ぺい率 | 容積率 |
|---|
| 第一種低層住居専用地域 | 一低専 | 低層住宅の良好な環境保護 | 住宅、小学校、診療所 | 店舗、事務所 | 30-60% | 50-200% |
| 第二種低層住居専用地域 | 二低専 | 主として低層住宅の環境保護 | 上記+150㎡以下の店舗 | 中学校、高校 | 30-60% | 50-200% |
| 第一種中高層住居専用地域 | 一中専 | 中高層住宅の良好な環境保護 | 住宅、病院、大学、500㎡以下の店舗 | 工場全般 | 30-60% | 100-500% |
| 第二種中高層住居専用地域 | 二中専 | 主として中高層住宅の環境保護 | 上記+1,500㎡以下の店舗 | 工場全般 | 30-60% | 100-500% |
| 第一種住居地域 | 一住居 | 住居の環境を保護 | 住宅、3,000㎡以下の店舗 | 工場(危険性大) | 50-80% | 100-500% |
| 第二種住居地域 | 二住居 | 主として住居の環境を保護 | 上記+パチンコ店等 | 工場(危険性大) | 50-80% | 100-500% |
| 準住居地域 | 準住居 | 道路沿道の住居と自動車関連施設の調和 | 上記+自動車関連施設 | 工場(危険性大) | 50-80% | 100-500% |
| 田園住居地域 | 田園住居 | 農業と調和した低層住宅環境の保護 | 住宅+農業関連施設 | 高層建物、大規模店舗 | 30-60% | 50-200% |
商業系・工業系用途地域(5種類)
| 用途地域名 | 略称 | 主な特徴 | 住宅建築 | 工場建築 | 建ぺい率 | 容積率 |
|---|
| 近隣商業地域 | 近商 | 近隣住民の日用品供給 | ○ | 小規模のみ○ | 60-80% | 100-500% |
| 商業地域 | 商業 | 商業その他業務の利便増進 | ○ | 一部制限 | 80% | 200-1300% |
| 準工業地域 | 準工業 | 環境悪化のおそれのない工業の利便 | ○ | 危険性少ないもの○ | 50-70% | 100-500% |
| 工業地域 | 工業 | 主として工業の利便増進 | ○ | ほぼ全て○ | 50-60% | 100-400% |
| 工業専用地域 | 工専 | 工業の利便増進専用 | ❌ | ほぼ全て○ | 30-60% | 100-400% |
🏗️ 開発許可制度一覧表
| 区域区分 | 許可必要面積 | 許可権者 | 主な例外 | 覚え方 |
|---|
| 市街化区域 | 1,000㎡以上 | 都道府県知事等 | 小規模開発は許可不要 | 「市街化は千(1000)」 |
| 市街化調整区域 | 原則全て | 都道府県知事等 | 農林漁業用等 | 「調整区域は全て」 |
| 非線引き区域 | 3,000㎡以上 | 都道府県知事等 | 一定規模以下は不要 | 「非線引きはさん(3)千」 |
| 都市計画区域外 | 10,000㎡以上 | 都道府県知事等 | 大規模開発のみ規制 | 「区域外は一(1)万」 |
📐 建築基準法重要計算項目
建ぺい率緩和計算表
| 緩和要件 | 緩和率 | 適用条件 | 併用時の扱い |
|---|
| 防火地域内の耐火建築物 | +10% | 防火地域+耐火構造 | 両方適用で+20% |
| 街角の敷地(角地等) | +10% | 特定行政庁指定 | 両方適用で+20% |
容積率制限計算フロー
【容積率決定の手順】
① 指定容積率を確認
↓
② 前面道路制限を計算
・住居系:道路幅員 × 4/10
・その他:道路幅員 × 6/10
↓
③ ①と②の小さい方を採用
↓
④ 最終容積率決定
【例】指定容積率300%、前面道路6m、住居系地域
前面道路制限:6m × 4/10 = 240%
→ 240% < 300% なので240%が適用
🌾 農地法許可制度詳細表
| 条文 | 行為内容 | 許可権者 | 主な許可要件 | 無許可の効果 | 覚え方 |
|---|
| 3条 | 農地→農地の権利移動 | 農業委員会 | ・農業従事要件<br>・下限面積要件<br>・効率利用要件 | 無効 | 「さん(3)条は農業委員会」 |
| 4条 | 農地の転用 | 都道府県知事等<br>(4ha超は大臣) | ・転用の確実性<br>・周辺農地への影響<br>・代替性の有無 | 原状回復命令等 | 「よん(4)条は転用」 |
| 5条 | 権利移動+転用 | 都道府県知事等<br>(4ha超は大臣) | 3条+4条の要件 | 無効+原状回復命令等 | 「ご(5)条は権利移動+転用」 |
📍 国土利用計画法事前届出制度
| 区域 | 届出面積(契約) | 届出期限 | 届出先 | 勧告の可能性 |
|---|
| 市街化区域 | 2,000㎡以上 | 契約締結日から2週間以内 | 市町村長 | あり |
| 市街化調整区域 | 5,000㎡以上 | 契約締結日から2週間以内 | 市町村長 | あり |
| 非線引き区域 | 5,000㎡以上 | 契約締結日から2週間以内 | 市町村長 | あり |
| 都市計画区域外 | 10,000㎡以上 | 契約締結日から2週間以内 | 市町村長 | あり |
⚖️ 民法等重要ポイント(14問)
👶 制限行為能力者完全比較表
| 類型 | 判断能力レベル | 成年年齢 | 単独有効行為 | 取消権者 | 催告制度 | 追認権者 |
|---|
| 未成年者 | 不完全 | 18歳 | 日常生活に関する行為 | 本人・法定代理人 | 1ヶ月以上 | 本人(成年後)・法定代理人 |
| 成年被後見人 | 常に欠く | – | 日用品購入その他日常生活行為 | 本人・成年後見人 | 1ヶ月以上 | 本人(判断能力回復時)・成年後見人 |
| 被保佐人 | 著しく不十分 | – | 重要な財産行為以外 | 本人・保佐人 | 1ヶ月以上 | 本人・保佐人 |
| 被補助人 | 不十分 | – | 家裁が定める特定行為以外 | 本人・補助人 | 1ヶ月以上 | 本人・補助人 |
🤝 意思表示の瑕疵と効果
| 意思表示の瑕疵 | 要件 | 効果 | 第三者保護 | 時効 |
|---|
| 心裡留保 | 真意でないことを知って意思表示 | 原則有効(相手方悪意・有過失なら無効) | – | – |
| 錯誤 | 表示行為・動機の錯誤+重要+無過失 | 取消可能 | 善意無過失の第三者保護 | 追認可能時から5年・行為時から20年 |
| 詐欺 | 故意に欺いて錯誤に陥らせる | 取消可能 | 善意無過失の第三者に対抗不可 | 追認可能時から5年・行為時から20年 |
| 強迫 | 害悪の告知により畏怖させる | 取消可能 | 第三者にも対抗可能 | 追認可能時から5年・行為時から20年 |
🏠 物権の種類と特徴一覧
用益物権詳細表
| 物権名 | 目的 | 対象物 | 対抗要件 | 譲渡性 | 存続期間 |
|---|
| 地上権 | 工作物・竹木所有目的で他人の土地を使用 | 他人の土地 | 登記 | 原則自由 | 当事者の設定次第 |
| 永小作権 | 耕作・牧畜目的で他人の土地を使用 | 他人の土地 | 登記 | 制限あり | 20年以上50年以下 |
| 地役権 | 自己の土地の便益のため他人の土地を使用 | 他人の土地 | 登記 | 要役地と一体 | 当事者の設定次第 |
| 入会権 | 共同利用目的 | 山林・原野等 | 慣習による | 制限あり | 慣習による |
担保物権比較表
| 物権名 | 発生原因 | 目的物の占有 | 対象物 | 実行方法 | 物上代位 |
|---|
| 留置権 | 法律の規定 | 必要 | 債権と牽連性ある物 | 競売申立て不可 | なし |
| 質権 | 当事者の合意 | 必要(不動産質は登記) | 動産・不動産・権利 | 競売・流質 | あり |
| 抵当権 | 当事者の合意 | 不要 | 不動産・地上権・永小作権 | 競売 | あり |
👨👩👧👦 相続制度詳細解説
法定相続人の順位と範囲
【相続人の決定フロー】
配偶者(常に相続人)
+
第1順位:子・代襲相続人(孫、ひ孫...)
↓(第1順位がいない場合)
第2順位:直系尊属(父母、祖父母...)
↓(第2順位がいない場合)
第3順位:兄弟姉妹・代襲相続人(甥・姪まで)
【代襲相続の範囲】
・子の系統:制限なし(孫→ひ孫→...)
・兄弟姉妹の系統:甥・姪まで(1代限り)
法定相続分計算表(具体例付き)
| 相続人構成 | 配偶者相続分 | その他相続分 | 計算例(遺産1,200万円) |
|---|
| 配偶者のみ | 全部(1/1) | – | 配偶者:1,200万円 |
| 配偶者+子2人 | 1/2 | 子全体で1/2(1人1/4) | 配偶者:600万円、子各300万円 |
| 配偶者+父母 | 2/3 | 父母で1/3(1人1/6) | 配偶者:800万円、父母各200万円 |
| 配偶者+兄弟2人 | 3/4 | 兄弟で1/4(1人1/8) | 配偶者:900万円、兄弟各150万円 |
| 子3人のみ | – | 全部を均等分割(1人1/3) | 子各400万円 |
遺留分制度詳細表
| 相続人構成 | 全体の遺留分 | 個人の遺留分計算 | 例(遺産1,000万円) |
|---|
| 直系尊属のみ | 1/3 | 1/3×法定相続分 | 父母各166.7万円 |
| その他の場合 | 1/2 | 1/2×法定相続分 | 配偶者250万円、子125万円 |
| 兄弟姉妹が相続人 | なし | なし | 遺留分なし |
⏰ 時効制度完全整理表
| 時効の種類 | 期間 | 起算点 | 中断事由 | 援用権者 | 放棄 |
|---|
| 取得時効(善意無過失) | 10年 | 占有開始時 | 裁判上の請求等 | 占有者等 | 完成後可能 |
| 取得時効(悪意・有過失) | 20年 | 占有開始時 | 裁判上の請求等 | 占有者等 | 完成後可能 |
| 債権の消滅時効(主観) | 5年 | 権利行使可能時 | 裁判上の請求等 | 債務者等 | 完成後可能 |
| 債権の消滅時効(客観) | 10年 | 権利発生時 | – | 債務者等 | 不可 |
| 不法行為(主観) | 3年 | 損害・加害者を知った時 | 裁判上の請求等 | 債務者等 | 完成後可能 |
| 不法行為(客観) | 20年 | 不法行為時 | – | 債務者等 | 不可 |
💰 税・その他分野(8問)
💸 不動産関連税制一覧表
不動産取得税(都道府県税)詳細
| 項目 | 内容 | 軽減措置 | 適用期限 |
|---|
| 課税対象 | 不動産の取得(売買・贈与・交換・建築等) | 相続による取得は非課税 | – |
| 課税標準 | 固定資産税評価額 | 住宅・土地は1/2特例 | 2027年3月31日まで |
| 標準税率 | 4% | 住宅・土地は3% | 2027年3月31日まで |
| 新築住宅控除 | 1,200万円控除 | 認定住宅は1,300万円 | – |
| 中古住宅控除 | 建築年により異なる | 昭和57年以降は1,200万円 | – |
固定資産税(市町村税)詳細
| 項目 | 内容 | 軽減措置 | 根拠 |
|---|
| 賦課期日 | 毎年1月1日 | 年途中売買でも1月1日所有者が納税義務者 | 地方税法343条 |
| 標準税率 | 1.4% | 市町村により制限税率1.7%まで設定可能 | 地方税法350条 |
| 納期 | 年4回(4月・7月・12月・2月) | 市町村により異なる・一括納付可能 | 各市町村条例 |
| 小規模住宅用地特例 | 課税標準×1/6 | 200㎡以下の住宅用地部分 | 地方税法349条の3の2 |
| 一般住宅用地特例 | 課税標準×1/3 | 200㎡超の住宅用地部分 | 地方税法349条の3の2 |
💰 所得税(譲渡所得)制度
譲渡所得の計算と税率
| 分類 | 所有期間 | 税率(復興税含む) | 計算式 |
|---|
| 短期譲渡所得 | 5年以下 | 39.63% | (譲渡価額-取得費-譲渡費用)×39.63% |
| 長期譲渡所得 | 5年超 | 20.315% | (譲渡価額-取得費-譲渡費用)×20.315% |
居住用財産の税制特例
| 特例名 | 要件 | 効果 | 併用 |
|---|
| 3,000万円特別控除 | 居住用財産の譲渡 | 譲渡所得から3,000万円控除 | 軽課と選択適用 |
| 軽課税率の特例 | 所有期間10年超の居住用財産 | 6,000万円以下の部分14.21% | 3,000万円控除と併用可 |
| 買換えの特例 | 居住用財産の買換え | 譲渡益の繰延べ | 他の特例と選択適用 |
📊 地価公示制度と都道府県地価調査比較
| 項目 | 地価公示 | 都道府県地価調査 |
|---|
| 実施主体 | 国(国土交通省土地鑑定委員会) | 各都道府県知事 |
| 根拠法令 | 地価公示法 | 国土利用計画法 |
| 基準日 | 毎年1月1日 | 毎年7月1日 |
| 公表時期 | 3月下旬 | 9月下旬 |
| 鑑定評価員数 | 2人以上 | 1人以上 |
| 対象地域 | 都市計画区域内の標準地 | 都市計画区域内外の基準地 |
| 価格の性格 | 正常価格 | 正常価格 |
🏦 住宅金融支援機構とフラット35
フラット35の特徴詳細表
| 項目 | 内容 | メリット | 注意点 |
|---|
| 金利タイプ | 全期間固定金利 | 金利変動リスクなし | 低金利時はデメリット |
| 融資期間 | 15年以上35年以下 | 長期返済可能 | 完済時年齢80歳まで |
| 融資限度額 | 8,000万円 | 高額融資可能 | 建設費・購入価額の100%以内 |
| 保証料 | 不要 | 初期費用軽減 | – |
| 保証人 | 不要 | 手続き簡素化 | – |
| 繰上返済手数料 | 不要 | 早期返済メリット大 | インターネット返済のみ |
| 団体信用生命保険 | 任意加入 | 保険料軽減可能 | 未加入時のリスク |
📋 景品表示法(重要ポイント)
不当表示の分類
| 表示分類 | 内容 | 具体例 | 罰則 |
|---|
| 優良誤認表示 | 商品・サービスの品質等を実際より著しく優良と誤認させる | 「最高級マンション」「完全無欠の物件」等 | 措置命令・課徴金 |
| 有利誤認表示 | 価格等の取引条件を実際より著しく有利と誤認させる | 「他社より必ず安い」「限定○○戸」等 | 措置命令・課徴金 |
| その他誤認されるおそれのある表示 | 一般消費者に誤認されるおそれがある表示として指定 | 不動産のおとり広告等 | 措置命令 |
🧮 計算問題完全マスター
📏 建ぺい率・容積率計算攻略法
基本計算公式
【基本公式】
建ぺい率 = 建築面積 ÷ 敷地面積 × 100(%)
容積率 = 延べ面積 ÷ 敷地面積 × 100(%)
【建築面積と延べ面積の違い】
・建築面積:建物を真上から見た面積(1階の床面積)
・延べ面積:各階の床面積の合計
複数用途地域計算のステップ解説
【ステップ1】敷地の面積按分
【ステップ2】各地域の建ぺい率・容積率を確認
【ステップ3】加重平均で計算
【計算例】
敷地面積:800㎡
A地域:500㎡(建ぺい率60%、容積率200%)
B地域:300㎡(建ぺい率50%、容積率150%)
建ぺい率 = (500×60% + 300×50%) ÷ 800
= (300 + 150) ÷ 800 = 56.25%
容積率 = (500×200% + 300×150%) ÷ 800
= (1,000 + 450) ÷ 800 = 181.25%
建ぺい率緩和の計算パターン
【緩和なし】
指定建ぺい率 = 60%
【緩和1つ適用】
指定建ぺい率60% + 緩和10% = 70%
【緩和2つ適用】
指定建ぺい率60% + 緩和20% = 80%
【上限を超える場合】
指定建ぺい率80% + 緩和20% = 100%(80%を超えても100%が上限)
💰 不動産取得税完全計算法
計算フローチャート
【Step1】課税標準の確定
固定資産税評価額
※住宅・土地は特例により1/2
↓
【Step2】控除額の確定
・新築住宅:1,200万円(認定住宅1,300万円)
・中古住宅:建築年により異なる
・土地:別途軽減あり
↓
【Step3】税率の適用
・一般:4%
・住宅・土地:3%(2027年3月31日まで)
↓
【Step4】税額計算
(課税標準 - 控除額) × 税率
↓
【Step5】土地の軽減(該当する場合)
Step4の税額から軽減額を差引き
住宅用土地の軽減計算詳細
【土地軽減額の計算】
以下のAまたはBのいずれか多い額
A:45,000円
B:土地1㎡当たりの価額 × 1/2 × 3% × 住宅床面積 × 2
【計算例】
土地:400㎡、評価額4,000万円(1㎡10万円)
住宅:120㎡
A = 45,000円
B = 10万円 × 1/2 × 3% × 120㎡ × 2
= 10万円 × 1/2 × 3% × 240㎡
= 36,000円
→ A(45,000円) > B(36,000円) なので45,000円を軽減
🏠 固定資産税住宅用地特例計算
特例適用の判定フロー
【判定ステップ】
住宅用地かどうか確認
↓
住宅用地の場合
↓
200㎡以下の部分→小規模住宅用地特例(1/6)
200㎡超の部分→一般住宅用地特例(1/3)
↓
特例適用後の課税標準×1.4%
具体的計算例
【例】住宅用地350㎡、評価額3,500万円
小規模住宅用地部分:200㎡
→ 2,000万円×1/6 = 約333万円
一般住宅用地部分:150㎡
→ 1,500万円×1/3 = 500万円
課税標準合計:833万円
固定資産税:833万円×1.4% = 約11.7万円
【特例なしの場合】
3,500万円×1.4% = 49万円
→ 約37万円の軽減効果
👨👩👧👦 相続分・遺留分計算マスター
法定相続分計算パターン集
【パターン1】配偶者+子2人
遺産:2,400万円
配偶者:2,400万円×1/2 = 1,200万円
子1:2,400万円×1/2×1/2 = 600万円
子2:2,400万円×1/2×1/2 = 600万円
【パターン2】配偶者+父母
遺産:1,800万円
配偶者:1,800万円×2/3 = 1,200万円
父:1,800万円×1/3×1/2 = 300万円
母:1,800万円×1/3×1/2 = 300万円
【パターン3】配偶者+兄弟3人
遺産:3,200万円
配偶者:3,200万円×3/4 = 2,400万円
兄弟1:3,200万円×1/4×1/3 = 約267万円
兄弟2:3,200万円×1/4×1/3 = 約267万円
兄弟3:3,200万円×1/4×1/3 = 約267万円
遺留分侵害額請求計算
【計算式】
遺留分侵害額 = 遺留分額 - 遺留分権利者の取得額
【例】遺産1,000万円、配偶者+子1人、遺言で配偶者が全て取得
子の遺留分額:1,000万円×1/2×1/4 = 125万円
子の取得額:0円
遺留分侵害額:125万円 - 0円 = 125万円
→子は配偶者に125万円の支払いを請求可能
⚡ 試験当日の完全マニュアル
⏰ 最適時間配分表(120分)
| 時間帯 | 分野(問題番号) | 配分時間 | 目標正答数 | 戦術ポイント |
|---|
| 13:00-13:30 | 宅建業法(問26-45) | 30分 | 18問以上 | ・確実に得点する分野<br>・迷わず即答<br>・18問取れれば合格8割確定 |
| 13:30-13:50 | 法令制限(問15-22) | 20分 | 6問以上 | ・暗記事項中心<br>・計算問題は慎重に<br>・用途地域は確実に |
| 13:50-14:10 | 税・その他(問46-50) | 20分 | 4問以上 | ・計算問題に時間をかける<br>・基本問題を確実に<br>・捨て問があっても気にしない |
| 14:10-14:45 | 民法等(問1-14) | 35分 | 8問以上 | ・最も時間をかける分野<br>・選択肢を慎重に検討<br>・分からない問題は飛ばす |
| 14:45-15:00 | 見直し・最終確認 | 15分 | 全問 | ・マークミスチェック<br>・空欄確認<br>・計算問題の再確認 |
📝 分野別解答戦略
宅建業法攻略法
【解答順序】
1. 免許・営業保証金(基本数字問題)
2. 35条・37条書面(頻出重要問題)
3. 宅建士・設置基準(計算問題)
4. 業務規制・報酬額(応用問題)
【注意点】
・数字問題は絶対に落とさない
・35条と37条の混同に注意
・計算問題は落ち着いて
・18問正解が目標ライン
法令制限攻略法
【解答順序】
1. 用途地域(13種類の分類)
2. 開発許可(面積基準)
3. 建築基準法(計算問題)
4. 農地法・国土利用計画法
【注意点】
・用途地域は完璧に覚える
・面積基準は語呂合わせで
・計算問題は公式を確認
・6問正解が目標ライン
民法等攻略法
【解答順序】
1. 制限行為能力者(確実に取れる問題)
2. 相続(計算問題含む)
3. 時効・意思表示(基本問題)
4. 物権・債権(応用問題)
【注意点】
・基本問題を確実に
・難問は深追いしない
・8問正解が目標ライン
・時間をかけて慎重に
✅ 試験当日チェックリスト
持参物最終確認表
| 区分 | 項目 | 重要度 | チェック | 備考 |
|---|
| 必須 | 受験票 | ★★★ | □ | 写真添付確認 |
| 必須 | 身分証明書(写真付き) | ★★★ | □ | 運転免許証・パスポート等 |
| 必須 | HBまたはBの鉛筆・シャープペンシル | ★★★ | □ | 3本以上用意 |
| 必須 | 消しゴム | ★★★ | □ | 2個以上用意 |
| 必須 | 時計 | ★★★ | □ | アラーム・計算機能なし |
| 推奨 | ハンカチ・ティッシュ | ★★☆ | □ | 机上に置ける |
| 推奨 | 目薬 | ★☆☆ | □ | 目の疲れ対策 |
| 推奨 | 膝掛け | ★☆☆ | □ | 会場の寒さ対策 |
試験直前30分の確認事項
【25分前】会場到着・座席確認
↓
【20分前】持参物最終チェック
↓
【15分前】重要数字の最終確認
・宅建業免許:5年
・営業保証金:本店1,000万円、支店500万円
・保証協会:本店60万円、支店30万円
・開発許可:市街化区域1,000㎡以上
↓
【10分前】深呼吸・リラックス
↓
【5分前】問題用紙配布・記名
↓
【開始】13:00試験開始
🎯 マークシート記入の鉄則
効率的記入方法
【5問ごと記入法】
問1-5解答 → マークシート記入
問6-10解答 → マークシート記入
問11-15解答 → マークシート記入
...
【メリット】
・記入忘れ防止
・番号ずれ防止
・ペース配分把握
マークミス防止チェック法
【記入時確認】
1. 問題番号とマーク番号の一致
2. 選択肢(1-4)の確認
3. しっかりと塗りつぶされているか
【見直し時確認】
1. 空欄がないか
2. 二重マークがないか
3. 消し残しがないか
❓ よくある質問(FAQ)
🤔 試験直前によくある不安と解決法
Q1: 宅建業法の35条書面と37条書面の違いが覚えられません
A1: 比較表で整理して覚えましょう
| 覚え方 | 35条書面 | 37条書面 |
|---|
| 語呂合わせ | 「さんご(35)は契約前」 | 「みなさん(37)契約後」 |
| 相手方 | お客さん(買主・借主)のみ | みんな(当事者全員) |
| 説明 | 説明あり | 説明なし |
Q2: 用途地域13種類が覚えられません
A2: 系統別に分類して覚えましょう
【住居系8種類】
低層専用(2種類)→ 一低専・二低専
中高層専用(2種類)→ 一中専・二中専
一般住居(2種類)→ 一住居・二住居
特殊(2種類)→ 準住居・田園住居
【商業系2種類】
近隣商業・商業
【工業系3種類】
準工業・工業・工業専用
Q3: 計算問題が苦手です
A3: 基本パターンを覚えて練習しましょう
【計算問題出題パターン】
1. 建ぺい率・容積率(ほぼ毎年出題)
2. 宅建士設置数(5人に1人以上)
3. 不動産取得税(軽減計算)
4. 相続分の計算
5. 報酬額の計算
【対策】
・公式を完璧に覚える
・過去問パターンを繰り返す
・電卓なしで計算練習
Q4: 時間が足りません
A4: 時間配分と解答順序を見直しましょう
【時間短縮のコツ】
1. 宅建業法から解く(得点しやすい)
2. 分からない問題は飛ばす
3. 計算問題は時間をかけすぎない
4. マークは5問ごとに記入
5. 見直し時間を必ず確保
【各分野の制限時間】
宅建業法:30分(1問1.5分)
法令制限:20分(1問2.5分)
民法等:35分(1問2.5分)
税その他:20分(1問2.5分)
見直し:15分
📚 勉強法についてのFAQ
Q5: 残り1週間で何を重点的に勉強すべきですか?
A5: 宅建業法と重要数字の暗記に集中しましょう
| 優先度 | 分野 | 学習内容 | 時間配分 |
|---|
| 最優先 | 宅建業法 | 35条・37条書面、重要数字 | 50% |
| 重要 | 法令制限 | 用途地域、開発許可面積 | 25% |
| 普通 | 税・その他 | 不動産取得税、固定資産税 | 15% |
| 低 | 民法等 | 制限行為能力者、相続 | 10% |
Q6: 過去問は何年分解けばいいですか?
A6: 最低5年分、できれば10年分解きましょう
【過去問学習の進め方】
1. 最新5年分を最低2回
2. 間違えた問題は3回以上
3. 分野別に弱点を分析
4. 出題傾向を把握
5. 時間を測って解く
【過去問活用のコツ】
・解説を必ず読む
・なぜ間違えたかを分析
・類似問題をまとめて解く
・本試験と同じ時間配分で
Q7: 模擬試験の点数が低くて不安です
A7: 模擬試験は学習の指針として活用しましょう
【模擬試験の活用法】
得点別対策:
30点未満 → 基本知識の再確認
30-35点 → 弱点分野の強化
35点以上 → 本試験で確実に合格
【重要なポイント】
・模擬試験の点数に一喜一憂しない
・間違えた問題の分析が重要
・本試験の時間配分を練習
・苦手分野の発見に活用
🎯 本試験についてのFAQ
Q8: 当日緊張してしまいそうです
A8: 事前準備と当日の心構えで対処しましょう
【緊張対策】
事前準備:
・会場下見
・持参物準備
・時間配分確認
・重要事項暗記
当日の心構え:
・早めに会場到着
・深呼吸でリラックス
・「18問取れば合格」と考える
・分からない問題は飛ばす
Q9: どの分野から解き始めるべきですか?
A9: 宅建業法から解くことを強く推奨します
【推奨解答順序】
1. 宅建業法(問26-45):30分
→ 最も得点しやすい分野
→ 18問取れれば合格に大きく近づく
2. 法令制限(問15-22):20分
→ 暗記中心で解きやすい
→ 計算問題も基本的
3. 税・その他(問46-50):20分
→ 問題数が少ない
→ 計算問題に集中
4. 民法等(問1-14):35分
→ 最も難しい分野
→ 時間をかけて慎重に
5. 見直し:15分
Q10: 合格ラインぎりぎりでも大丈夫ですか?
A10: 合格点を1点でも上回れば確実に合格です
【合格への考え方】
・合格点は相対評価(上位約17%)
・1点差でも合格は合格
・完璧を目指さず確実に点を取る
・宅建業法18問+他分野19問=37点で十分
【最後のアドバイス】
・自分を信じる
・基本問題を確実に
・最後まで諦めない
・見直し時間を大切に
🚀 最終合格メッセージ
🎯 合格への3つの鉄則
1️⃣ 宅建業法で18問以上取る
→ これで合格の80%が決まる
2️⃣ 基本問題を確実に正解する
→ 難問は捨てる勇気を持つ
3️⃣ 最後まで諦めない
→ 1点が合否を分ける試験
📊 最終確認:重要数字ベスト20
| 順位 | 項目 | 数字 | 覚え方 |
|---|
| 1 | 宅建業免許有効期間 | 5年 | 「ご年間」 |
| 2 | 営業保証金(本店) | 1,000万円 | 「千万円」 |
| 3 | 営業保証金(支店) | 500万円 | 「ごひゃく万円」 |
| 4 | 保証協会(本店) | 60万円 | 「ろくじゅう万円」 |
| 5 | 保証協会(支店) | 30万円 | 「さんじゅう万円」 |
| 6 | 宅建士設置基準 | 5人に1人以上 | 「ごにんにひとり」 |
| 7 | 開発許可(市街化区域) | 1,000㎡以上 | 「せんへーべー」 |
| 8 | 開発許可(市街化調整区域) | 原則全て | 「全て」 |
| 9 | 開発許可(非線引き区域) | 3,000㎡以上 | 「さんぜんへーべー」 |
| 10 | 用途地域の種類 | 13種類 | 「じゅうさんしゅるい」 |
| 11 | 成年年齢 | 18歳 | 「じゅうはっさい」 |
| 12 | 取得時効(善意無過失) | 10年 | 「じゅうねん」 |
| 13 | 取得時効(悪意・有過失) | 20年 | 「にじゅうねん」 |
| 14 | 債権の消滅時効 | 5年 | 「ごねん」 |
| 15 | 配偶者+子の相続分 | 各1/2 | 「はんぶんずつ」 |
| 16 | 不動産取得税率 | 4%(住宅・土地3%) | 「よんぱー(さんぱー)」 |
| 17 | 固定資産税標準税率 | 1.4% | 「いってんよんぱー」 |
| 18 | 住宅用地特例(小規模) | 1/6 | 「ろくぶんのいち」 |
| 19 | 住宅用地特例(一般) | 1/3 | 「さんぶんのいち」 |
| 20 | 地価公示基準日 | 1月1日 | 「いちがつついたち」 |
🌟 あなたの合格を確信する理由
✅ この記事を最後まで読んだあなたの学習意欲 ✅ 表と図で整理された重要ポイントの理解 ✅ 計算問題の解法パターンの習得 ✅ 時間配分と解答戦略の準備 ✅ よくある間違いポイントの把握
📱 関連記事・リンク
🔗 公式サイト・重要リンク
📚 おすすめ学習ツール
- 宅建過去問アプリ – スキマ時間活用
- 法令集アプリ – 条文確認
- 宅建学習動画 – 理解促進
🎯 試験後の活用
このブログは宅建士登録後の実務でも活用できる内容を含んでいます。合格後もぜひご参照ください。
🏆 最後に
🔥 宅建試験合格への道のりは決して簡単ではありませんが、正しい知識と戦略があれば必ず突破できます!
この記事に込めた情報と愛情が、あなたの合格への最後の一押しとなることを心から願っています。
試験当日は自信を持って臨み、これまでの努力を信じて最後まで戦い抜いてください!
あなたの宅建士合格を心から応援しています!📋✨
🏅 合格の報告をお待ちしています!
最終更新:2025年9月11日
2025年宅建試験対応・法改正反映済み
🏷️ タグ・キーワード
#宅建試験 #宅建業法 #法令制限 #民法 #税法 #重要数字 #計算問題 #合格点 #勉強法 #直前対策 #暗記事項 #宅建士 #不動産 #国家資格 #2025年試験

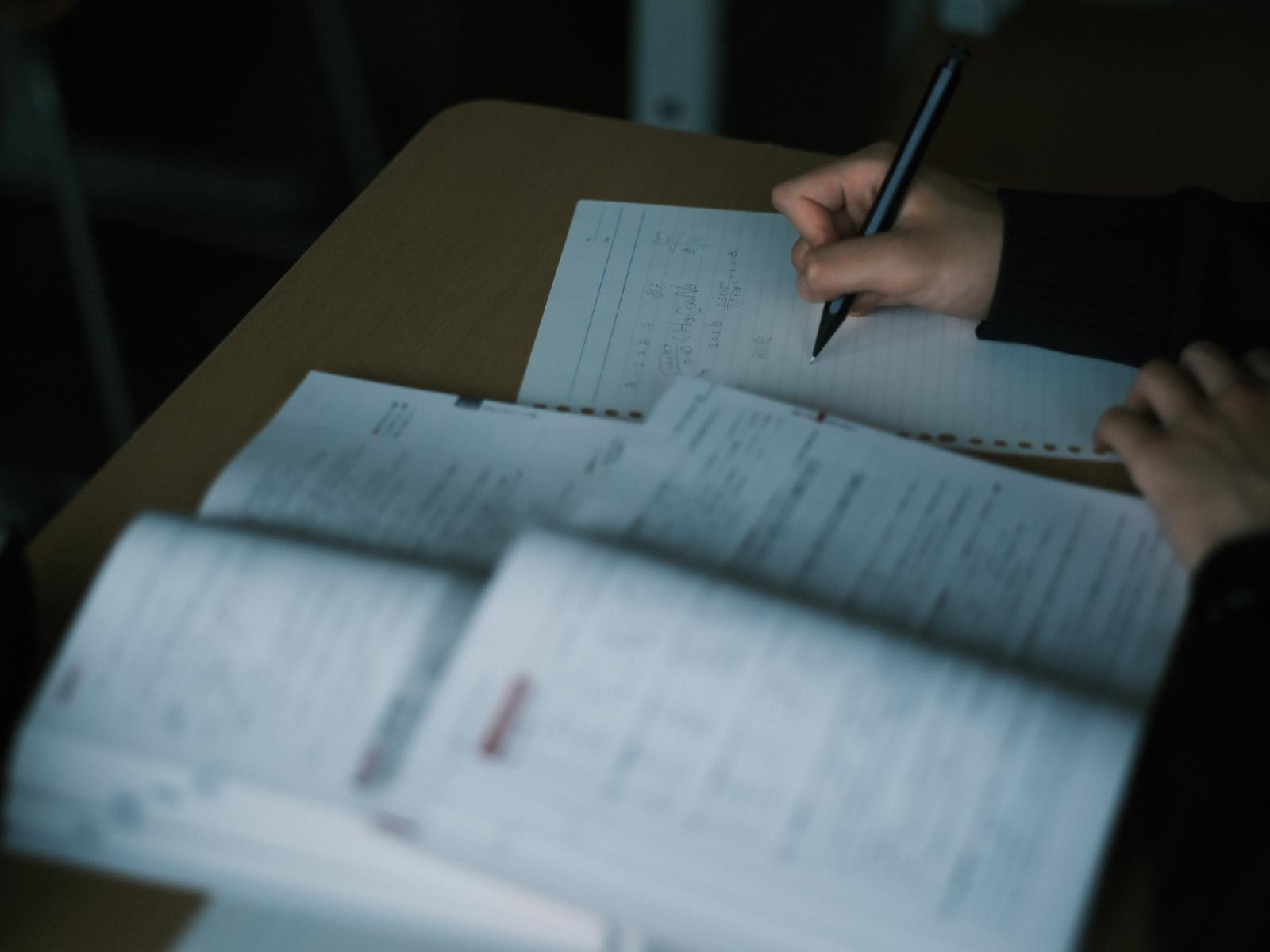


コメント