💭 受験生Aさん「相続って難しそう…覚えることが多すぎて不安です」
🎓 宅建講師「大丈夫!相続は基本パターンを覚えれば確実に得点できる分野よ。一緒に攻略していきましょう!」
はじめに:なぜ宅建試験で相続が重要なのか?
宅地建物取引士試験を受験される皆さん、相続の勉強は順調に進んでいますか?
😰 受験生Bさん「相続って民法の一部でしょ?そんなに重要なの?」
📚 合格者Cさん「それが大間違い!相続は宅建試験の隠れた得点源なんです」
こんな風に思われるかもしれませんが、それは大きな間違いです!実は相続は宅建試験において非常に重要で、しかも得点しやすい分野なんです。
相続が宅建試験で重要な5つの理由
┌─────────────────────────────────┐
│ 宅建試験における相続の重要性 │
├─────────────────────────────────┤
│ ✅ 毎年必ず出題(出題率100%) │
│ ✅ 不動産実務に直結(相談件数30%) │
│ ✅ 基本問題の正解率75%(得点源) │
│ ✅ 他分野との関連深い(登記・税務) │
│ ✅ 実務での応用範囲が広い │
└─────────────────────────────────┘
💡 宅建講師「過去10年間、相続分野は100%出題されているの。これを落とすのはもったいないわよ!」
過去10年間の出題実績
| 年度 | 問題番号 | 出題内容 | 正解率 |
|---|---|---|---|
| 2023年 | 問28 | 相続人・相続分 | 78% |
| 2022年 | 問29 | 遺言・遺留分 | 65% |
| 2021年 | 問28 | 相続放棄・限定承認 | 72% |
| 2020年 | 問29 | 代襲相続 | 81% |
| 2019年 | 問28 | 法定相続分 | 75% |
| 2018年 | 問29 | 遺留分 | 58% |
| 2017年 | 問28 | 代襲相続・相続分 | 69% |
| 2016年 | 問29 | 遺言の効力 | 63% |
| 2015年 | 問28 | 相続人の範囲 | 84% |
| 2014年 | 問29 | 相続放棄 | 77% |
😊 合格者Cさん「私は相続で1点取れたおかげで合格できました。基本問題なら確実に正解できますよ!」
第1章:相続の基本知識を完全マスター
🤔 受験生Aさん「相続って何から始めればいいの?」
🎓 宅建講師「まずは『相続とは何か』から始めましょう。これが分かれば後はスムーズよ!」
1-1. 相続とは何か?
相続の基本構造
被相続人(亡くなった人)
↓
相続開始
↓
┌─────────────────┐
│ 相続財産(遺産) │
├─────────────────┤
│ ✅ プラス財産 │
│ ・現金・預金 │
│ ・不動産 │
│ ・株式・債券 │
│ ・動産 │
├─────────────────┤
│ ❌ マイナス財産 │
│ ・借金・債務 │
│ ・保証債務 │
│ ・税金滞納 │
└─────────────────┘
↓
相続人へ承継
⚠️ 注意ポイント「相続はプラスもマイナスも全部引き継ぐのがポイント。借金も相続しちゃうのよ!」
💭 受験生Bさん「えー!借金まで相続するの?それは困るなあ…」
😌 宅建講師「大丈夫。相続放棄という制度があるから安心して。後で詳しく説明するわね」
1-2. 相続開始の要件と効果
| 相続開始の原因 | 要件 | 効果発生時期 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 自然死亡 | 病気・事故・老衰 | 死亡時 | 最も一般的 |
| 認定死亡 | 死体未発見だが死亡確実 | 官庁認定時 | 災害時など |
| 失踪宣告 | 生死不明7年(危難1年) | 宣告時 | 死亡とみなす |
📝 暗記のコツ「失踪宣告は『普通は7年、危険は1年』で覚えよう!」
1-3. 法定相続人の完全図解
🤯 受験生Aさん「相続人って誰がなれるの?家族全員?」
🎓 宅建講師「いえいえ、法律で決まっているの。順番があるから整理して覚えましょう!」
相続人の優先順位システム
配偶者
↓
【常に相続人】
血族相続人の順位
↓
┌─────────────────┐
│ 第1順位 │
│ 直系卑属 │
│ │
│ 子 → 孫 → ひ孫 │
│ (無限に代襲) │
└─────────────────┘
↓(第1順位がいない場合)
┌─────────────────┐
│ 第2順位 │
│ 直系尊属 │
│ │
│父母 → 祖父母 → 曾祖父母│
│ (近い世代が優先) │
└─────────────────┘
↓(第1・2順位がいない場合)
┌─────────────────┐
│ 第3順位 │
│ 兄弟姉妹 │
│ │
│ 兄弟姉妹 → 甥姪 │
│ (1代のみ代襲) │
└─────────────────┘
💡 重要ポイント「配偶者は『常に』相続人!これは超重要な基本事項よ」
🤔 受験生Bさん「順位があるってことは、上位の人がいると下位の人は相続できないの?」
✅ 宅建講師「その通り!第1順位がいれば第2・3順位は相続人になれません」
具体的な相続関係図パターン
パターン1:標準的な家族
被相続人A
│
┌───┼───┐
配偶者B 子C 子D
│
┌──┴──┐
孫E 孫F
相続人:B、C、D(孫E・Fは相続人ではない)
😊 合格者Cさん「孫がいても子どもが生きていれば孫は相続人にならない。これポイントです!」
パターン2:代襲相続が発生する場合
被相続人A
│
┌───┼───┐
配偶者B 子C 子D(先死)
│
┌──┴──┐
孫E 孫F
相続人:B、C、E、F(孫E・Fが子Dを代襲相続)
⭐ 代襲相続「子どもが先に亡くなっている場合、その子(孫)が代わりに相続人になるの」
パターン3:複数世代の代襲相続
被相続人A
│
┌───┼───┐
配偶者B 子C 子D(先死)
│
┌──┴──┐
孫E(先死) 孫F
│
ひ孫G
相続人:B、C、F、G(ひ孫Gが孫Eを代襲相続)
🎯 宅建講師「直系卑属(子・孫・ひ孫)は何代でも代襲できるの。これが兄弟姉妹と違うところよ」
パターン4:兄弟姉妹の相続
被相続人A(配偶者・子なし)
│
┌───┼───┐
兄B 姉C 弟D(先死)
│
┌──┴──┐
甥E 姪F
相続人:B、C、E、F(甥姪E・Fが弟Dを代襲相続)
⚠️ 要注意「兄弟姉妹の代襲相続は甥・姪まで。その子(大甥・大姪)は代襲できません!」
😲 受験生Aさん「えー、なんで兄弟姉妹だけ1代なの?」
📖 宅建講師「法律で決まっているの。『子は無限、兄弟は1代』って覚えましょう」
1-4. 法定相続分の詳細計算表
🧮 受験生Bさん「相続分の計算が一番苦手…」
😊 合格者Cさん「大丈夫!パターンを覚えちゃえば簡単ですよ」
基本パターン一覧
| 相続人構成 | 配偶者 | 血族全体 | 血族1人当たり |
|---|---|---|---|
| 配偶者+子 | 1/2 | 1/2 | 1/2÷子の人数 |
| 配偶者+直系尊属 | 2/3 | 1/3 | 1/3÷尊属の人数 |
| 配偶者+兄弟姉妹 | 3/4 | 1/4 | 1/4÷兄弟姉妹の人数 |
| 配偶者のみ | 1/1 | – | – |
| 子のみ | – | 1/1 | 1/1÷子の人数 |
| 直系尊属のみ | – | 1/1 | 1/1÷尊属の人数 |
| 兄弟姉妹のみ | – | 1/1 | 1/1÷兄弟姉妹の人数 |
📝 暗記の極意「配偶者の相続分『1/2 → 2/3 → 3/4』この順番で覚えて!」
🤔 受験生Aさん「なんで1/2、2/3、3/4なの?」
🎓 宅建講師「子→直系尊属→兄弟姉妹の順で、血族との関係が遠くなると配偶者の取り分が増えるのよ」
具体的計算例
ケース1:配偶者と子3人の場合
遺産総額:6,000万円
配偶者:6,000万円 × 1/2 = 3,000万円
子A: 6,000万円 × 1/2 × 1/3 = 1,000万円
子B: 6,000万円 × 1/2 × 1/3 = 1,000万円
子C: 6,000万円 × 1/2 × 1/3 = 1,000万円
合計:6,000万円 ✅
💰 計算のコツ「配偶者はまず1/2、残りを子どもで等分。これで間違えなし!」
ケース2:配偶者と父母の場合
遺産総額:3,000万円
配偶者:3,000万円 × 2/3 = 2,000万円
父: 3,000万円 × 1/3 × 1/2 = 500万円
母: 3,000万円 × 1/3 × 1/2 = 500万円
合計:3,000万円 ✅
👥 受験生Bさん「父母が両方いる時は1/3を半分ずつね」
ケース3:配偶者と兄弟姉妹の場合
遺産総額:4,000万円
配偶者:4,000万円 × 3/4 = 3,000万円
兄: 4,000万円 × 1/4 × 1/2 = 500万円
姉: 4,000万円 × 1/4 × 1/2 = 500万円
合計:4,000万円 ✅
🎯 宅建講師「配偶者と兄弟姉妹の組み合わせが一番配偶者の取り分が多いの」
半血兄弟姉妹の特殊計算
全血と半血の相続分比較
| 関係性 | 相続分の比率 | 計算例(兄弟分1/4の場合) |
|---|---|---|
| 全血兄弟姉妹 | 2 | 1/4 × 2/3 = 1/6 |
| 半血兄弟姉妹 | 1 | 1/4 × 1/3 = 1/12 |
🤨 受験生Aさん「全血?半血?なにそれ?」
📚 宅建講師「全血は父母が同じ兄弟、半血は片親だけ同じ兄弟のこと。半血の相続分は半分よ」
具体例:配偶者、全血兄、半血姉の場合
遺産総額:3,600万円
配偶者:3,600万円 × 3/4 = 2,700万円
全血兄:3,600万円 × 1/4 × 2/3 = 600万円
半血姉:3,600万円 × 1/4 × 1/3 = 300万円
合計:3,600万円 ✅
⚠️ 試験のワナ「半血兄弟姉妹の問題はよく出るから要注意!2:1の比率を忘れずに」
第2章:宅建試験で狙われる重要ポイント
😤 受験生Bさん「基本は分かったけど、試験ではどこが狙われるの?」
🎯 合格者Cさん「代襲相続と遺留分は毎年のように出ますよ。しっかり対策しましょう!」
2-1. 代襲相続の完全攻略
代襲相続発生原因の比較表
| 原因 | 直系卑属 | 兄弟姉妹 | 代襲の範囲 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 死亡 | ✅ | ✅ | 無限代 vs 1代のみ | 最も一般的 |
| 欠格 | ✅ | ✅ | 無限代 vs 1代のみ | 故意の犯罪など |
| 廃除 | ✅ | ✅ | 無限代 vs 1代のみ | 家庭裁判所の審判 |
| 相続放棄 | ❌ | ❌ | 代襲なし | 初めから相続人でない |
| 失踪宣告 | △ | △ | 場合による | 判例により判断 |
🔥 超重要「相続放棄では代襲相続は起きない!これは絶対に覚えて」
😵 受験生Aさん「えー、なんで相続放棄だけ代襲がないの?」
🎓 宅建講師「相続放棄すると『初めから相続人でなかった』ことになるからよ。存在しない人の代襲はできないでしょ?」
代襲相続の世代図解
直系卑属の代襲相続(無限代)
被相続人A
│
子B(先死)
│
孫C(先死)
│
ひ孫D(先死)
│
やしゃごE ← 代襲相続可能!
♾️ 無限代襲「子どもの系統は何代でも代襲可能。やしゃご、来孫、昆孫…無限に続くのよ」
兄弟姉妹の代襲相続(1代のみ)
被相続人A
│
兄B(先死)
│
甥C ← 代襲相続可能
│
甥の子D ← 代襲相続不可❌
⛔ 1代制限「兄弟姉妹の代襲は甥・姪まで。その先は代襲できません」
😅 受験生Bさん「なんで兄弟姉妹だけ制限があるの?」
📖 宅建講師「あまり遠い親族まで相続権を認めるのは適切じゃないからよ。法律の政策的判断ね」
2-2. 相続承認・放棄の完全比較表
💸 受験生Aさん「借金が多い相続はどうしたらいいの?」
🛡️ 宅建講師「相続放棄や限定承認という制度があるの。それぞれの特徴を覚えましょう」
| 項目 | 単純承認 | 限定承認 | 相続放棄 |
|---|---|---|---|
| 承継範囲 | 全財産 | プラス財産の限度 | 一切承継しない |
| 責任範囲 | 無限責任 | 有限責任 | 責任なし |
| 手続期限 | 制限なし | 3ヶ月以内 | 3ヶ月以内 |
| 手続方法 | 特別な手続不要 | 家庭裁判所申述 | 家庭裁判所申述 |
| 共同性 | 不要 | 全員共同必要 | 単独可能 |
| 撤回 | 不可 | 原則不可 | 原則不可 |
| 代襲相続 | 発生 | 発生 | 発生しない |
⏰ 期限注意「相続放棄・限定承認は3ヶ月以内!これを過ぎると単純承認になっちゃう」
🤝 受験生Bさん「限定承認は全員でやらなきゃいけないのね」
😌 宅建講師「そう。一人でも反対したら限定承認はできないの。だから実際にはあまり使われないのよ」
相続承認・放棄の判断フローチャート
相続開始を知る
↓
┌─────────────┐
│ プラス財産 > │
│ マイナス財産?│
└─────────────┘
↓ YES
┌─────────────┐
│ 単純承認 │
│ (何もしない) │
└─────────────┘
↓ NO
┌─────────────┐
│ プラス財産 ≒ │
│ マイナス財産?│
└─────────────┘
↓ YES
┌─────────────┐
│ 限定承認 │
│ (相続人全員) │
└─────────────┘
↓ NO
┌─────────────┐
│ 相続放棄 │
│ (個人単独) │
└─────────────┘
💡 判断の基準「借金が多いなら放棄、微妙なら限定承認、得するなら単純承認」
2-3. 遺言制度の詳細比較
📜 受験生Aさん「遺言っていろんな種類があるんでしょ?」
✍️ 宅建講師「主に3種類あるの。それぞれの特徴を整理しましょう」
遺言方式の特徴比較表
| 項目 | 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 |
|---|---|---|---|
| 作成者 | 遺言者本人 | 公証人 | 遺言者本人 |
| 証人 | 不要 | 2人以上必要 | 2人以上必要 |
| 自筆要件 | 全文・日付・氏名 | 署名のみ | 署名のみ |
| 費用 | 安い(印紙代等) | 高い(公証人手数料) | 中程度 |
| 秘密性 | 高い | 低い(証人が知る) | 高い |
| 安全性 | 低い(紛失・偽造) | 高い(原本保管) | 中程度 |
| 検認 | 必要(保管制度除く) | 不要 | 必要 |
| 無効リスク | 高い | 低い | 中程度 |
🏆 おすすめ度「確実性なら公正証書、手軽さなら自筆証書、秘密なら秘密証書」
💰 受験生Bさん「公正証書遺言はお金かかるのね」
💪 合格者Cさん「でも一番確実ですよ。無効になるリスクが少ないから」
自筆証書遺言の要件詳細
2019年改正前後の比較
| 項目 | 改正前 | 改正後(2019年~) |
|---|---|---|
| 遺言本文 | 全文自筆必須 | 全文自筆必須 |
| 財産目録 | 全文自筆必須 | パソコン作成可 |
| 各ページ署名 | 不要 | 各ページ署名・押印必要 |
| 法務局保管 | 制度なし | 2020年開始 |
| 検認 | 必須 | 保管制度利用時は不要 |
🆕 法改正ポイント「2019年から財産目録はパソコンでOK!でも各ページに署名・押印が必要よ」
😊 受験生Aさん「パソコンで作れるようになったのは便利ね」
⚠️ 宅建講師「でも本文は手書き必須。財産目録だけパソコンOKなの。間違えないでね」
2-4. 遺留分制度の完全理解
😠 受験生Bさん「全財産を愛人に譲るって遺言があったら、家族は何ももらえないの?」
🛡️ 宅建講師「それを防ぐのが遺留分制度よ。家族の最低限の取り分を保障するの」
遺留分権利者と遺留分率
遺留分権利者の判定
┌─────────────────────┐
│ 配偶者 │
│ 【遺留分あり】 │
└─────────────────────┘
┌─────────────────────┐
│ 直系卑属 │
│ (子・孫・ひ孫) │
│ 【遺留分あり】 │
└─────────────────────┘
┌─────────────────────┐
│ 直系尊属 │
│ (父母・祖父母) │
│ 【遺留分あり】 │
└─────────────────────┘
┌─────────────────────┐
│ 兄弟姉妹 │
│ (甥姪) │
│ 【遺留分なし❌】 │
└─────────────────────┘
🚫 超重要「兄弟姉妹に遺留分はなし!これは絶対に覚えて」
🤔 受験生Aさん「なんで兄弟姉妹だけ遺留分がないの?」
📖 宅建講師「兄弟姉妹は血のつながりが遠いからよ。配偶者や子どもの生活保障が優先なの」
遺留分率の計算表
| 相続人構成 | 全体の遺留分率 | 各人の遺留分率 |
|---|---|---|
| 直系尊属のみ | 1/3 | 1/3 × 法定相続分 |
| その他すべて | 1/2 | 1/2 × 法定相続分 |
🧮 計算公式「個人の遺留分 = 遺留分率 × その人の法定相続分」
具体的遺留分計算例
ケース1:配偶者と子2人
相続財産:1億円
法定相続分:配偶者1/2、各子1/4
全体の遺留分率:1/2
各人の遺留分:
・配偶者:1億円 × 1/2 × 1/2 = 2,500万円
・子A: 1億円 × 1/2 × 1/4 = 1,250万円
・子B: 1億円 × 1/2 × 1/4 = 1,250万円
💡 受験生Bさん「法定相続分が分かれば遺留分も計算できるのね」
ケース2:父母のみ
相続財産:6,000万円
法定相続分:各父母1/2
全体の遺留分率:1/3
各人の遺留分:
・父:6,000万円 × 1/3 × 1/2 = 1,000万円
・母:6,000万円 × 1/3 × 1/2 = 1,000万円
🎯 宅建講師「直系尊属のみの場合は遺留分率が1/3になることに注意!」
遺留分侵害額請求の手続きフロー
遺留分の侵害発覚
↓
┌─────────────────┐
│ 侵害額の計算 │
│ 遺留分額-取得額 │
└─────────────────┘
↓
┌─────────────────┐
│ 受遺者・受贈者 │
│ に対する請求 │
└─────────────────┘
↓
┌─────────────────┐
│ 金銭での弁済 │
│ (2019年改正後) │
└─────────────────┘
↓
┌─────────────────┐
│ 時効期間 │
│ 知った日から1年間 │
│ 相続開始から10年間 │
└─────────────────┘
⏰ 時効に注意「遺留分侵害額請求は1年以内!忘れると権利を失っちゃう」
第3章:過去問徹底分析と解法テクニック
📊 受験生Aさん「過去問を分析すると傾向が見えてくるの?」
📈 合格者Cさん「はい!出やすい分野が分かるから効率的に勉強できますよ」
3-1. 過去10年出題傾向の詳細分析
分野別出題頻度グラフ
出題頻度(過去10年間)
法定相続人・相続分 ████████ 80%
代襲相続 ██████ 60%
遺言 █████ 50%
相続承認・放棄 ████ 40%
遺留分 ███ 30%
その他 ██ 20%
0% 25% 50% 75% 100%
🔥 最頻出「法定相続人・相続分は8割の確率で出題。ここは絶対に落とせません!」
難易度別正解率分析
| 難易度レベル | 出題数 | 平均正解率 | 主な出題内容 |
|---|---|---|---|
| 基本問題 | 6問 | 75-85% | 基本的な相続人・相続分 |
| 標準問題 | 3問 | 55-75% | 代襲相続・遺留分 |
| 応用問題 | 1問 | 35-55% | 複雑な計算・特殊事例 |
🎯 戦略「基本問題を確実に取って、標準問題で差をつける。応用問題は取れればラッキー」
😅 受験生Bさん「応用問題は捨てちゃっていいの?」
🎓 宅建講師「基本問題を完璧にしてから応用に挑戦しましょう。欲張りすぎは禁物よ」
年度別難易度推移
正解率推移(相続分野)
90%| ●
|
80%| ● ● ●
|
70%| ● ● ●
| ●
60%| ●
| ●
50%|
└─────────────────────────
2014 2016 2018 2020 2022 2024
年度
📉 傾向分析「最近は少し難しくなってる傾向。でも基本ができていれば大丈夫!」
3-2. 頻出問題パターンと完全解法
🧩 受験生Aさん「問題のパターンって決まってるの?」
🎲 合格者Cさん「はい!だいたい決まったパターンがあります。慣れれば解きやすいですよ」
パターン1:複雑な相続関係の整理
頻出問題例
家族構成図による出題例
被相続人A
│
┌───┼───┬───┐
配偶者B 長男C 次男D 三男E
(先死) (先死)
│ │
┌──┴─┐ ├──┬──┐
孫F 孫G 孫H 孫I 孫J
解法の手順
- 配偶者の確認 → B(常に相続人)
- 第1順位の存在確認 → 長男C、次男D・三男Eの代襲相続人
- 代襲相続人の特定 → 孫F・G(Dの代襲)、孫H・I・J(Eの代襲)
- 最終相続人 → B、C、F、G、H、I、J
📝 解法のコツ「家系図を書いて、生きている人と死んでいる人を整理。代襲を確認して最終判断」
😊 受験生Bさん「図を書くと分かりやすいね」
パターン2:法定相続分の段階的計算
計算手順テンプレート
| ステップ | 作業内容 | 例:配偶者+子3人 |
|---|---|---|
| Step1 | 相続人構成の確認 | 配偶者+子 |
| Step2 | 基本割合の適用 | 配偶者1/2、子全体1/2 |
| Step3 | 同順位内の分割 | 各子:1/2÷3人=1/6 |
| Step4 | 検算 | 1/2+1/6×3=1 ✅ |
✅ 検算重要「最後に合計が1になるか必ず確認!これで計算ミスを防げるわ」
パターン3:代襲相続の適用判定フロー
代襲相続発生の判定フロー
被相続人より先に死亡?
↓ YES
┌─────────────────┐
│ 直系卑属 or 兄弟姉妹?│
└─────────────────┘
↓
直系卑属 兄弟姉妹
↓ ↓
┌─────────────┐ ┌─────────────┐
│ 無限に代襲 │ │ 1代のみ代襲 │
│ (何世代でも)│ │ (甥姪まで) │
└─────────────┘ └─────────────┘
🌊 フロー活用「迷ったらこのフローに沿って考える。間違いなし!」
3-3. 引っかけ問題の完全対策
🪤 受験生Aさん「引っかけ問題にいつも騙されちゃう…」
😈 宅建講師「引っかけパターンを覚えちゃえば逆に得点源になるのよ」
頻出引っかけパターン一覧表
| 引っかけの種類 | 間違いやすい記述 | 正しい知識 | 出題頻度 |
|---|---|---|---|
| 代襲の世代 | 「兄弟姉妹の代襲は2代まで」 | 1代(甥姪)のみ | ⭐⭐⭐ |
| 遺留分権利者 | 「全相続人に遺留分がある」 | 兄弟姉妹は対象外 | ⭐⭐⭐ |
| 承認放棄期限 | 「6ヶ月以内に決定」 | 3ヶ月以内 | ⭐⭐ |
| 限定承認の共同性 | 「個人で可能」 | 相続人全員共同 | ⭐⭐ |
| 相続放棄の効果 | 「他の相続人に移転」 | 初めから相続人でない | ⭐⭐ |
🎯 対策法「よくある引っかけを暗記して、問題文でそのワードが出たら注意深く読む」
😤 受験生Bさん「こんなに引っかけがあるなんてズルい」
😏 合格者Cさん「でも知ってれば逆にサービス問題ですよ」
引っかけ回避のチェックリスト
問題文チェックポイント
□ 「兄弟姉妹」が出たら遺留分なしを確認
□ 「代襲相続」が出たら世代制限を確認
□ 「相続放棄」が出たら期限・効果を確認
□ 「限定承認」が出たら共同性を確認
□ 数字が出たら基本数値と比較確認
📋 チェック習慣「このチェックリストを頭に入れて、問題を解く時は必ず確認」
第4章:実務に活かせる相続知識
💼 受験生Aさん「宅建士になったら相続の知識はどう使うの?」
🏢 現役宅建士「相続関連の相談は本当に多いです。お客様に的確なアドバイスができるようになりますよ」
4-1. 相続登記実務の要点
相続登記義務化の詳細
制度の概要(2024年4月施行)
| 項目 | 内容 | 期限 | 罰則 |
|---|---|---|---|
| 義務対象者 | 相続により所有権取得した相続人 | 3年以内 | 10万円以下の過料 |
| 申請期限 | 相続開始・所有権取得を知った日から | 3年以内 | 正当な理由があれば免除 |
| 適用範囲 | 2024年4月以前の相続も対象 | 2027年3月31日まで | 経過措置あり |
🆕 新制度「2024年から相続登記が義務化!宅建士は必ず知っておくべき制度よ」
💸 受験生Bさん「10万円の過料って結構痛いね」
😰 現役宅建士「そうなんです。だからお客様には早めの登記をおすすめしています」
相続登記の必要書類チェックリスト
相続登記必要書類一覧
【基本書類】
□ 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
□ 相続人全員の戸籍謄本
□ 相続人全員の住民票
□ 固定資産評価証明書
□ 登記申請書
【遺産分割による場合】
□ 遺産分割協議書
□ 相続人全員の印鑑証明書
【遺言による場合】
□ 遺言書
□ 検認済証明書(公正証書遺言以外)
📋 書類準備「書類集めが大変だから、司法書士さんと連携することが多いです」
4-2. 相続税の基礎知識体系
相続税基礎控除額の計算表
| 法定相続人数 | 基礎控除額 | 配偶者控除適用後の実質非課税額 |
|---|---|---|
| 1人 | 3,600万円 | 1億6,000万円 |
| 2人 | 4,200万円 | 1億6,000万円 |
| 3人 | 4,800万円 | 1億6,000万円 |
| 4人 | 5,400万円 | 1億6,000万円 |
| 5人 | 6,000万円 | 1億6,000万円 |
計算式:3,000万円 + 600万円 × 法定相続人数
💰 お得情報「配偶者がいれば実質1億6千万円まで非課税。これは覚えておくと便利」
😊 受験生Aさん「意外と非課税枠が大きいのね」
🏠 現役宅建士「でも都心の不動産だと超えることもあるから要注意です」
主要な相続税特例一覧
| 特例名 | 適用要件 | 軽減効果 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 配偶者の税額軽減 | 配偶者が取得 | 1億6千万円or法定相続分まで非課税 | 申告が必要 |
| 小規模宅地等の特例 | 居住・事業用宅地 | 80%減額(330㎡まで) | 継続居住要件あり |
| 未成年者控除 | 20歳未満の相続人 | (20歳-相続時年齢)×10万円 | 法定相続人のみ |
| 障害者控除 | 障害者の相続人 | (85歳-相続時年齢)×10万円 | 一般・特別の区別あり |
🏡 小規模宅地「自宅の土地なら8割減額。これで相続税が大幅に減ることも」
4-3. 相続不動産売買の実務フロー
🏘️ 受験生Bさん「相続した不動産を売るときはどうするの?」
📝 現役宅建士「権利関係の確認が一番重要です。トラブルを避けるためにしっかりチェックします」
売買取引における確認事項
相続不動産売買の確認フロー
┌─────────────────┐
│ 権利関係の確認 │
├─────────────────┤
│ ✓ 相続登記の完了 │
│ ✓ 遺産分割の完了 │
│ ✓ 共有者全員の同意 │
└─────────────────┘
↓
┌─────────────────┐
│ 必要書類の準備 │
├─────────────────┤
│ ✓ 相続関係説明図 │
│ ✓ 遺産分割協議書 │
│ ✓ 印鑑証明書 │
└─────────────────┘
↓
┌─────────────────┐
│ 重要事項説明の実施 │
├─────────────────┤
│ ✓ 相続経緯の説明 │
│ ✓ 権利関係の明示 │
│ ✓ リスクの説明 │
└─────────────────┘
共有不動産の処理方法比較
| 処理方法 | メリット | デメリット | 適用場面 |
|---|---|---|---|
| 協議分割 | 迅速・低コスト | 合意が困難な場合も | 相続人間の関係良好 |
| 調停分割 | 裁判所の関与で公正 | 時間・費用がかかる | 協議が困難 |
| 審判分割 | 強制的解決 | 関係悪化のリスク | 調停不調 |
| 共有持分売却 | 単独で処理可能 | 価格が安くなりがち | 早期現金化希望 |
⚠️ トラブル予防「共有不動産は揉めやすい。早めの解決をおすすめしています」
第5章:効率的学習法と暗記テクニック
📚 受験生Aさん「効率よく覚える方法はある?」
🧠 学習コーチ「はい!科学的な暗記法を使えば効率的に覚えられますよ」
5-1. 学習スケジュールの最適化
3ヶ月間学習計画表
| 期間 | 学習目標 | 主な内容 | 時間配分 | 達成度測定 |
|---|---|---|---|---|
| 第1ヶ月 | 基礎理解 | 相続の基本概念<br>法定相続人・相続分 | 理論70%<br>問題30% | 基本問題正解率70% |
| 第2ヶ月 | 応用力強化 | 代襲相続・遺言<br>遺留分・承認放棄 | 理論50%<br>問題50% | 標準問題正解率60% |
| 第3ヶ月 | 実践演習 | 過去問演習<br>弱点克服 | 理論30%<br>問題70% | 全問題正解率75% |
📅 計画の立て方「最初は理論中心、だんだん問題演習の割合を増やしていく」
🎯 受験生Bさん「3ヶ月で75%正解率って現実的?」
💪 合格者Cさん「私もこのプランで合格しました。継続すれば必ず達成できます」
週間学習サイクル
週間学習サイクル(例:2時間/日)
月曜日:新単元の理論学習(2時間)
火曜日:前日の復習+問題演習(1時間+1時間)
水曜日:弱点分野の補強学習(2時間)
木曜日:過去問演習(2時間)
金曜日:週間総復習(2時間)
土曜日:模擬試験・実力確認(3時間)
日曜日:間違い直し・知識整理(2時間)
週間合計:14時間
⏰ 学習コーチ「毎日少しずつ続けることが大切。週14時間なら十分合格レベルに達します」
5-2. 効果的暗記テクニック集
語呂合わせ暗記表
| 覚える内容 | 語呂合わせ | 詳細 |
|---|---|---|
| 法定相続分 | 「配偶者は にぶんのいち、さんぶんの2、よんぶんの3」 | 1/2→2/3→3/4の順 |
| 代襲相続 | 「子は無限、兄弟は1回」 | 直系卑属vs兄弟姉妹 |
| 遺留分率 | 「尊属さん、その他に」 | 直系尊属1/3、その他1/2 |
| 承認放棄期限 | 「相続は3ヶ月で決めよう」 | 3ヶ月以内 |
| 遺留分権利者 | 「遺留分は兄弟だけ留守」 | 兄弟姉妹は対象外 |
🎵 語呂合わせ活用「恥ずかしがらずに声に出して覚える。リズムに乗せると忘れにくい」
😄 受験生Aさん「『遺留分は兄弟だけ留守』って面白い!」
🎭 学習コーチ「インパクトのある語呂合わせほど記憶に残りやすいんです」
図表活用法
相続分暗記表(分数一覧)
配偶者 + 相手方 = 配偶者の相続分
配偶者 + 子 = 1/2
配偶者 + 尊属 = 2/3
配偶者 + 兄弟 = 3/4
覚え方:「1/2 → 2/3 → 3/4」
(分子が1つずつ増える)
📊 視覚活用「表やグラフにすると覚えやすい。手書きで何度も書くとさらに効果的」
代襲相続範囲の暗記図
直系卑属:子→孫→ひ孫→やしゃご→...(∞)
兄弟姉妹:兄弟姉妹→甥姪(終了)
覚え方:「直系は直進、兄弟は1駅」
🚆 イメージ記憶「電車のイメージで覚える。直系は急行で直進、兄弟は各駅停車で1駅で終点」
5-3. 問題演習の戦略的アプローチ
📝 受験生Bさん「問題を解くコツってある?」
🎯 問題解決のプロ「選択肢の特徴を知ると正解率がグンと上がりますよ」
正解選択肢の特徴分析
正解になりやすいキーワード
| カテゴリ | 特徴的表現 | 例文 |
|---|---|---|
| 条件限定 | 「原則として」「一般的に」 | 「原則として相続人となる」 |
| 例外言及 | 「ただし~の場合を除く」 | 「ただし代襲相続の場合を除く」 |
| 具体的数値 | 明確な期間・割合 | 「3ヶ月以内」「1/2」 |
| 正確な法的効果 | 法律上の正確な表現 | 「初めから相続人でなかった」 |
✅ 正解の特徴「あいまいでない、具体的で正確な表現が正解になりやすい」
不正解になりやすいキーワード
| カテゴリ | 危険な表現 | 理由 |
|---|---|---|
| 絶対表現 | 「必ず」「絶対に」「常に」 | 例外を認めない |
| 曖昧表現 | 「適当な」「相当な」 | 法的根拠不明 |
| 極端な例 | 「すべて」「一切」「全く」 | 現実的でない |
| 混同表現 | 制度の特徴を混同 | 知識の混乱を誘う |
❌ 要注意表現「『絶対に』『必ず』『常に』が出たら疑ってかかる」
🤔 受験生Aさん「でも例外もあるでしょ?」
📖 問題解決のプロ「もちろん。でも8割くらいの確率で当たります。統計的な傾向として覚えておくと便利」
問題文読解のチェックリスト
問題文読解の5ステップ
□ Step1:家族構成を図に整理
□ Step2:死亡・生存の状況確認
□ Step3:代襲相続の発生確認
□ Step4:相続人の最終確定
□ Step5:選択肢との照合
📋 システマチック「この5ステップを必ず守る。慌てずに順序立てて解く」
第6章:最新法改正と出題予想
🆕 受験生Aさん「法改正があると試験に出やすいって聞いたけど本当?」
📰 法律の専門家「はい!改正された部分は出題されやすい傾向があります。要注意です」
6-1. 重要改正事項の整理
民法相続法改正の概要(2018年改正・2019-2020年施行)
| 改正項目 | 施行日 | 改正内容 | 宅建試験への影響 |
|---|---|---|---|
| 配偶者居住権 | 2020年4月 | 配偶者の居住保障 | 今後出題の可能性 |
| 自筆証書遺言 | 2019年1月 | 財産目録PC作成可 | 出題済み |
| 遺留分制度 | 2019年7月 | 金銭債権化 | 理論出題の可能性 |
| 相続人以外の貢献 | 2019年7月 | 特別寄与料制度 | 基本知識として |
🔥 改正チェック「新しい制度は試験委員も注目している。出題確率高いから要チェック」
配偶者居住権制度の詳細
制度の仕組み
従来の制度
┌─────────────┐
│ 不動産所有権 │
│ (居住権+財産権) │
│ ↓ │
│ 配偶者が取得 │
└─────────────┘
新制度(配偶者居住権)
┌─────────────┐ ┌─────────────┐
│ 配偶者居住権 │ │ 所有権 │
│ (居住のみの権利) │ │ (財産的価値) │
│ ↓ │ │ ↓ │
│ 配偶者取得 │ │ 子が取得 │
└─────────────┘ └─────────────┘
🏠 新制度の狙い「配偶者の居住を確保しつつ、子どもも財産を相続できる。画期的な制度よ」
権利の特徴
| 項目 | 配偶者居住権 | 配偶者短期居住権 |
|---|---|---|
| 存続期間 | 終身または期間指定 | 6ヶ月間 |
| 成立要件 | 遺産分割・遺言・家裁審判 | 法律上当然に成立 |
| 譲渡性 | 不可 | 不可 |
| 登記 | 可能(対抗要件) | 不要 |
💭 受験生Bさん「複雑そうだけど、宅建試験に出る?」
🎯 法律の専門家「基本的な仕組みだけ理解しておけば十分。細かい規定まで覚える必要はありません」
6-2. 2025年試験出題予想
分野別出題予想度
2025年出題予想ランキング
━━━━━━━━━━ 90% 法定相続人・相続分
━━━━━━━━━ 80% 代襲相続
━━━━━━━ 60% 遺留分
━━━━━ 50% 相続承認・放棄
━━━━ 40% 遺言制度
━━ 20% 配偶者居住権
━ 10% 特別寄与料
0% 25% 50% 75% 100%
🔮 予想の根拠「過去の傾向と法改正の状況を総合的に分析した結果です」
😊 受験生Aさん「基本分野の出題予想が高いなら安心」
🎯 予想のプロ「そうです。基本をしっかり押さえれば高得点が期待できます」
重点対策問題の優先度
Aランク(絶対出題・満点必須)
- 基本的な法定相続人の範囲
- 基本的な法定相続分の計算
- 代襲相続の世代制限
- 遺留分権利者の範囲
- 相続放棄の基本的効果
🥇 Aランク対策「ここは100%正解を目指す。落とすと合格が厳しくなる」
Bランク(高確率出題・確実に取りたい)
- 半血兄弟姉妹の相続分
- 複雑な代襲相続関係
- 遺留分の計算
- 限定承認の特徴
- 遺言の方式
🥈 Bランク対策「ここで差がつく。80%以上の正解率を目指そう」
Cランク(出題可能性・差がつく問題)
- 配偶者居住権の基本
- 特別寄与料制度
- 遺言執行者の権限
- 相続回復請求権
- 寄与分制度
🥉 Cランク対策「余裕があれば挑戦。でもA・Bランクが優先」
🎓 合格者Cさん「私はA・Bランクに集中して合格しました。欲張らないのがコツです」
第7章:実戦模擬問題集
📝 受験生Aさん「実際の問題で実力を試したい!」
🎯 模試の先生「はい!レベル別に問題を用意しました。チャレンジしてみましょう」
7-1. 基本レベル問題(正解率目標80%)
問題1:法定相続人の判定
家族関係図
被相続人A
│
┌───┼───┐
配偶者B 長男C 次男D(先死)
│
┌──┴──┐
孫E 孫F
Aが死亡した場合の法定相続人を全て選びなさい。
- B・C
- B・C・D
- B・C・E・F
- B・C・D・E・F
🤔 考え方のヒント「配偶者は常に相続人。次男Dは死亡しているから代襲相続を考える」
解答:3 解説:
- 配偶者Bは常に相続人
- 長男Cは第1順位の相続人
- 次男Dは死亡しているため、その子E・Fが代襲相続
- 死亡者Dは相続人にはならない
✅ ポイント「死亡した人は相続人にならない。その子が代襲相続する」
問題2:法定相続分の計算
被相続人の相続人が配偶者、全血の兄、半血の姉の場合、各人の法定相続分として正しい組み合わせを選びなさい。
| 選択肢 | 配偶者 | 全血の兄 | 半血の姉 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3/4 | 1/8 | 1/8 |
| 2 | 3/4 | 1/6 | 1/12 |
| 3 | 2/3 | 1/6 | 1/6 |
| 4 | 1/2 | 1/4 | 1/4 |
🧮 計算のヒント「配偶者と兄弟姉妹なら配偶者3/4。全血:半血=2:1の比率で計算」
解答:2 解説:
- 配偶者と兄弟姉妹:配偶者3/4、兄弟姉妹全体1/4
- 全血:半血=2:1の比率
- 全血兄:1/4×2/3=1/6
- 半血姉:1/4×1/3=1/12
📝 受験生Bさん「半血は全血の半分って覚えればいいのね」
7-2. 標準レベル問題(正解率目標60%)
問題3:複雑な代襲相続
被相続人Aには配偶者B、長男C、次男D、三男Eがいた。次男Dは相続開始前に死亡し、その子(Aの孫)F、Gがいる。孫Fも相続開始前に死亡し、その子(Aのひ孫)Hがいる。三男Eは相続放棄をした。
この場合の相続人と各人の法定相続分として正しいものを選びなさい。
解答選択肢
1. 相続人:B・C・G・H
法定相続分:B(1/2)、C(1/6)、G(1/6)、H(1/6)
2. 相続人:B・C・E・G・H
法定相続分:B(1/2)、C(1/8)、E(1/8)、G(1/8)、H(1/8)
3. 相続人:B・C・G・H
法定相続分:B(1/2)、C(1/4)、G(1/8)、H(1/8)
4. 相続人:B・C・G
法定相続分:B(1/2)、C(1/4)、G(1/4)
🧩 複雑な問題の解き方「まず相続人を確定してから相続分を計算。ステップを踏んで解く」
💭 考えるポイント「三男Eの相続放棄、孫Fの死亡による再代襲相続に注意」
解答:1 解説:
- 次男Dの代襲:孫G、ひ孫H(孫Fの代襲)
- 三男Eは相続放棄により初めから相続人でない
- 相続人:B・C・G・H(4人)
- 配偶者B:1/2、子の部分1/2を3人で分割
- C・G・H:各1/6
🎯 重要ポイント「相続放棄した人は初めから存在しないものとして計算」
7-3. 応用レベル問題(正解率目標40%)
問題4:遺留分の計算
被相続人Aの相続財産は1億2000万円で、相続人は配偶者Bと子C・Dの3人である。Aは遺言により全財産を配偶者Bに相続させるとしていた。
この場合の子C・Dの遺留分侵害額として正しいものを選びなさい。
計算過程
相続財産:1億2000万円
法定相続分:B(1/2)、C(1/4)、D(1/4)
全体の遺留分率:1/2
各人の遺留分:
・配偶者B:1億2000万円×1/2×1/2=3000万円
・子C:1億2000万円×1/2×1/4=1500万円
・子D:1億2000万円×1/2×1/4=1500万円
遺留分侵害額:
・子C:1500万円-0円=1500万円
・子D:1500万円-0円=1500万円
🧮 計算の手順「法定相続分→遺留分→実際取得額→侵害額の順で計算」
- 各子1000万円
- 各子1500万円
- 各子2000万円
- 各子3000万円
解答:2
💡 模試の先生「遺留分の計算は複雑だけど、手順を覚えれば必ず解けます」
😊 受験生Aさん「計算過程を見れば理解できました!」
まとめ:相続で確実に得点するための最終チェック
🏁 受験生たち「いよいよ最終チェックね!」
🎓 宅建講師「はい!最後に重要ポイントを整理しましょう。これで相続は完璧よ」
重要ポイントの最終確認表
法定相続人・相続分(出題率90%)
┌─────────────────────────────┐
│ 重要度:★★★★★ │
│ │
│ □ 配偶者は常に相続人 │
│ □ 血族相続人の順位制 │
│ □ 代襲相続:直系卑属∞、兄弟姉妹1代│
│ □ 法定相続分:1/2、2/3、3/4 │
│ □ 半血兄弟姉妹は全血の1/2 │
└─────────────────────────────┘
🥇 最重要「ここを落とすと合格が厳しい。必ず満点を取りましょう」
相続の承認・放棄(出題率60%)
┌─────────────────────────────┐
│ 重要度:★★★★ │
│ │
│ □ 期限:相続開始を知った日から3ヶ月│
│ □ 放棄:単独可能、初めから相続人でない│
│ □ 限定承認:全員共同、有限責任 │
│ □ 放棄→代襲相続なし │
└─────────────────────────────┘
⏰ 期限注意「3ヶ月の期限は絶対に覚えて。よく引っかけで出されます」
遺留分制度(出題率50%)
┌─────────────────────────────┐
│ 重要度:★★★ │
│ │
│ □ 兄弟姉妹に遺留分なし │
│ □ 遺留分率:直系尊属のみ1/3、その他1/2│
│ □ 個人の遺留分=率×法定相続分 │
│ □ 請求期限:知った日から1年 │
└─────────────────────────────┘
🚫 絶対暗記「兄弟姉妹に遺留分なし。これは100%覚えて」
直前期の学習優先順位
ラスト1ヶ月の学習配分
学習時間配分(直前1ヶ月)
基本事項の暗記 40% ████████████
過去問反復演習 35% ██████████
模擬試験実施 15% ████
弱点補強 10% ██
合計:100%
📈 効率的配分「基本事項の暗記に一番時間をかける。これが合格の鍵よ」
💪 受験生Bさん「基本重視で頑張ります!」
試験直前1週間のチェックリスト
知識の最終確認
- [ ] 法定相続人の順位と範囲
- [ ] 基本的な法定相続分(1/2、2/3、3/4)
- [ ] 代襲相続の世代制限(直系卑属∞、兄弟姉妹1代)
- [ ] 遺留分権利者(兄弟姉妹は対象外)
- [ ] 相続放棄の期限と効果(3ヶ月、初めから相続人でない)
解法テクニックの確認
- [ ] 家族関係図の書き方
- [ ] 相続分計算の手順
- [ ] 引っかけパターンの識別
- [ ] 選択肢の消去法
- [ ] 時間配分の練習
📋 最終チェック「この項目を全部クリアできれば合格間違いなし」
最終メッセージ
🎯 宅建講師「皆さん、相続の勉強お疲れ様でした。最後にメッセージを」
相続は宅建試験の中でも最も確実に得点できる分野の一つです。
💪 励ましのメッセージ「複雑に見えても、基本パターンを覚えれば必ず解けるようになります」
複雑に見える相続制度も、基本的な仕組みを理解すれば必ず解けるようになります。大切なのは:
1. 基本を確実にマスターすること
- 完璧を目指さず、基本8割を確実に
😊 合格者Cさん「私も最初は難しく感じたけど、基本を繰り返し覚えたら得意分野になりました」
2. 過去問で出題パターンを覚えること
- 新しい問題も基本パターンの応用
📝 過去問マスター「過去問を10年分やれば、どんな問題が出ても対応できます」
3. 引っかけに慣れること
- よくある間違いを事前に把握
🪤 引っかけ対策のプロ「引っかけパターンを知っていれば、逆にサービス問題になります」
4. 継続的な復習を心がけること
- 一度覚えても必ず忘れるもの
🔄 復習の大切さ「エビングハウスの忘却曲線に負けないよう、定期的に復習しましょう」
相続分野をマスターすることで、宅建試験合格に大きく近づくだけでなく、将来宅建士として活躍する際の重要な基礎知識となります。
🌟 未来への投資「宅建士になってからも相続の知識は必ず役に立ちます。今の努力は将来への投資よ」
「相続を制する者は宅建を制す」
🏆 最後の応援「この言葉を胸に、最後まで諦めずに頑張ってください!」
この言葉を胸に、最後まで諦めずに頑張ってください!
皆さんの合格を心から応援しています。
👏 全員で応援「頑張れ受験生!みんなで応援してるよ〜」
参考資料
重要条文早見表
| 条文 | 内容 | 暗記ポイント |
|---|---|---|
| 民法887条 | 子の相続権・代襲相続 | 直系卑属は無限代襲 |
| 民法889条 | 直系尊属・兄弟姉妹の相続権 | 兄弟姉妹は1代のみ代襲 |
| 民法900条 | 法定相続分 | 1/2、2/3、3/4を暗記 |
| 民法915条 | 承認・放棄の期間 | 3ヶ月以内 |
| 民法1028条 | 遺留分の帰属・割合 | 兄弟姉妹は対象外 |
📚 条文活用「条文番号まで覚える必要はないけど、内容は正確に理解しておこう」
学習に役立つWebサイト
- 法務省:相続登記が義務化されます
- 国税庁:相続税のあらまし
- 裁判所:相続放棄・限定承認の申述
🌐 追加学習「余裕があれば公的サイトで最新情報もチェック」
この記事が宅建試験の相続対策に役立つことを願っています。継続的な学習こそが合格への最短ルートです。頑張ってください!
🎉 最後の最後まで「応援してます!絶対合格しましょう〜」

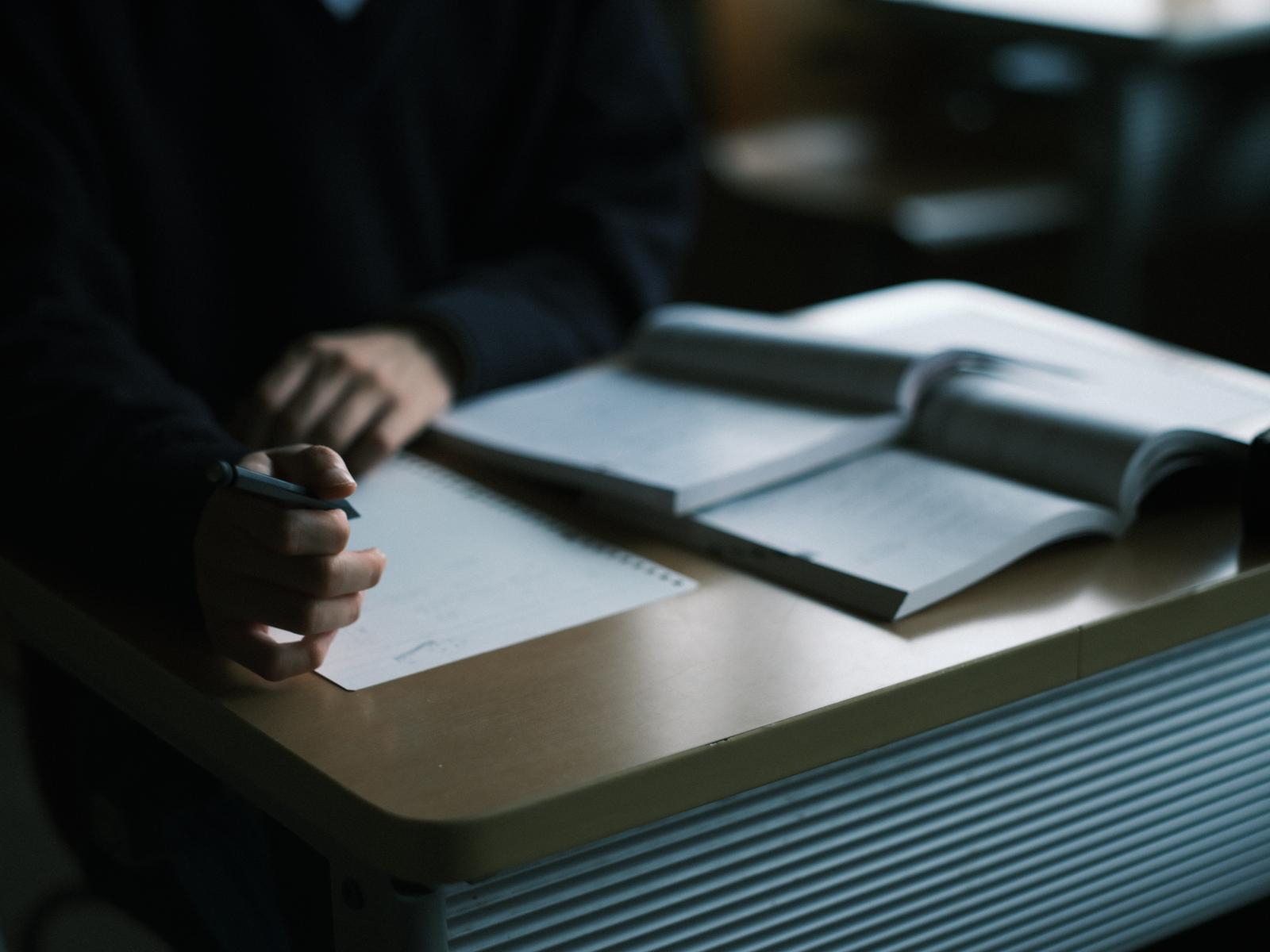


コメント